結局は気持ちの問題になる。
この記事には広告が含まれています。
書くことは、気持ちの問題だ
なんとこの7月で、ブログを始めて10年が経つようです。あっという間に時間が過ぎていったことに驚きつつ、「どうしてこんなに続けることができたのだろうか?」と考えることも増えました。
これまで何度か、「ブログを書くのに使っているマシン」や「写真を撮るのに使うカメラ」にフォーカスして紹介する記事は書いてきました。けれども、そもそも僕がどのような「メンタル」でブログを向き合ってきたかという観点でブログ環境を紹介したことはありませんでした。
もちろん、マシンやカメラは重要ですよ。作業効率化や執筆する記事の質に直接影響するので、いいマシン、そしていいカメラを使うというのは、とっても重要。
そして、いいマシン・いいカメラを使った先にあるのは、「どういう気持ちでブログ・noteに向き合うか」ということでして。つまりメンタルの部分。いいマシン・いいカメラを持っていても、それを使ってアウトプットしなければ、持っている意味は半減してしまいます。
目的は、記事を量産すること。いいマシン・いいカメラを使うことは、その目的を達成するための手段。どんなに手段が揃っていても、それを活かす気持ちが整っていなければ、目的には辿り着けない。「自分にしっくりくるマシンやカメラ」を使うことでメンタルを整え、自分をコントロールしたいのです。
「どうすれば書こうと思えるか?」——このような問いを常に意識し、自分の環境を改善するように試行錯誤を繰り返してきたメンタルこそが、ブログやnoteを長く続ける上で大事なものだったのです。
書く気になれない日だってあるし、忙しさにかまけて画面すら開かない日もあります。でも、それでもまた書き始められるのは、「書ける自分」に戻すためのちょっとした仕掛けが、日常の中に散りばめられているからなんですよね。
今回は、そんなメンタルを整えるための環境づくりについて、10年間書き続けてきた僕なりの視点で紹介してみようと思います。
もくじ
iPadという“狭さ”が、集中を連れてくる
僕は普段iMacで記事を書いていますが、たまに気分転換したくてiPadで書くこともあるんです。ちょうど先日記事にしたように、ダイニングテーブルの上でiPadを縦向きに置き、お気に入りのキーボードを繋いで記事を書くと、驚くほどすらすらと文章を紡ぎ出すことができる。
「これってなぜだろう?」を考えたとき、先日の記事では5つの項目を挙げました。
- シングルタスクに向くiPad
- iPadOSのしっとりとした安定性
- 縦向きの一覧性
- スタンド+縦向きで目線が上がる
- お気に入りのキーボードが使える
詳細は記事を読んでいただければと思いますが、ざっくりまとめると、iPadは目的のアプリが全画面で広がる環境が基本になっているから、視線の高さやキーボードにこだわることで、余計なことに邪魔されない集中できる環境を作り出すことができるってこと。

つまり、デバイスの使い方を工夫したり、好きなデバイスを使うことによって、「自分のテンションやモチベーションをコントロールできる環境」を作り出す。その結果、自ずと集中力を引き出すことになり、やりたかった作業が捗る。
そして、これを単にライフハックの話に終わらせたくなくて。もっと大きな、たとえば「人生における課題や悩み」を解決するための方法にだってなれると思うんです。自分を集中へ誘うことができる方法を知っていれば、もっと高いところを目指すことができるかもしれない。
僕の場合は、「作業に使うデバイス=環境」に対してこだわりを持つことで、心地よく手を動かすことができる環境を作り出す。そうすると、まるでスイッチが入ったかのように、文章を書くことに熱中することができる。デバイスを起点にメンタルを整える。
目的から逆算したとき、それを達成するための手段として「いいマシン」「いいカメラ」があるのであれば、そこに投資してみるのもいいのではないか。そう思うんですよ。
気分を切り替える“儀式”の存在
それでも、書こうと思っても、すぐには書けないときがあります。そんなときは、何も考えずに執筆画面を開いても、ただ白い画面がそこにあるだけで、指が動かない。そういうときこそ大事なのが、気分を切り替えるための儀式だと僕は思っています。
たとえば、コーヒーを淹れる。いつものドリップ道具を取り出して、お湯を沸かし、豆の香りに包まれながら数分間ぼーっと過ごす。なんてことない時間だけど、不思議とその間に頭の中がリセットされて、書くモードに切り替わっていく。
あるいは、僕はFLEXISPOTのスタンディングデスクを使っているんですが、座っていてもどうしても集中できないときは、思い切ってスタンディングモードに切り替えて立って作業することもあります。体を動かすことで頭が冴えてきて、停滞していた思考が再び流れ出すような感覚になるんです。
こうした行動って、何か大きな作業を始める前に深呼吸したり、身なりを整えたりするのと似ています。つまり、気持ちのスイッチは、体を通じて切り替わることが多いんだと思う。
僕の場合、「書こうと思っているけど、まだ書けていない」っていう中途半端な状態が全然落ち着かない。だから、書けない日こそ「とりあえず整える」ことだけでもやってみる。それだけで、「よし、いけるかも」と思える日もある。
書くことって、習慣よりも、たぶん流れなんですよね。で、その流れの入口に立つための、ちょっとした儀式を用意しておくと、かなり助けられる場面があると思うんです。

“どこで書くか”で気分を変える
書くことに向き合うとき、「どこで書くか」って、実はかなり重要だったりします。僕は基本的には自宅のデスクでブログ・noteを書くことが多いけれど、たまには環境を変えることで自分を整えることができます。
ずっと同じ場所、同じ机、同じ椅子で書いていると、どうしても気が滅入ってしまう。思考もルーティンに縛られてしまって、なんだか言葉が平坦になっていく感じがするんですよ。なんかこう、書いているのに、活力がなくなっていくというか。
だから僕は、たまに「場所を変える」ということをしています。たとえば、書斎のデスクじゃなくて、ダイニングテーブル。そこにiPadとお気に入りのキーボードだけを持っていくと、ちょっとした非日常感が生まれて、言葉の流れが変わってくる。
もっと大きく気分を変えたいときは、カフェに行くこともあります。スタバの端っこの席に座って、コーヒーを飲みながら静かに書く。横や後ろに人がいたら落ち着かないから、席は重要です。そして、周囲のざわめきがBGMのように感じられて、不思議と集中できたりするんですよ。
もちろん、どこでも書けるわけじゃありません。集中力が必要なときは静かな場所がいいし、アイデアを練りたいときはあえて喧騒の中に身を置いた方が浮かんでくることもある。
でも、その「自分にとってどんな場所が今ふさわしいか?」を感じ取ることができると、書く前からリズムが整っていくように思います。まさに今も、デスクのiMacではどうも集中できなくて、iPadを持ってリビングのソファに避難してきました。
執筆環境って、ハードウェアのことだけじゃなくて、「空間」もその一部なんですよね。だから、書けないときは、まず場所を変えてみる。それだけで、何かが変わるかもしれません。
道具は“支えてくれる存在”であればいい
長く書き続けてきたからこそ感じるのは、「道具って、信頼できる相棒みたいなものだな」ということ。
特にキーボード。文章を書くときは書かせません。だから自分の手に馴染むものを使いたい。僕はHHKBやMX Mechanical Miniを使い分けているけれど、どちらが優れているかというよりも、その日の気分や作業場所に合わせて、しっくりくるものを選びたいと思っています。
特にHHKBの静電容量の打鍵感は、それをタイピングすること自体に幸せを感じるし、気持ちを切り替えるきっかけになる。MX Mechanical Miniの柔らかい中に芯がある、カタカタとした小気味よい打鍵感も心地よい。こうしてタイピングそのものが楽しくなることで、自然と文章に向かっていけるような気がするんですよね。
でも一方で、「いい道具を使えば、勝手に書けるようになる」ということでもありません。どんなに高価なガジェットを揃えても、自分の気持ちが整っていなければ、ただの物体になってしまう。道具は、あくまでも自分を整えるためのきっかけであって、主役ではないと思うんです。
たとえば、カフェにHHKBを持っていくことはありません。iPad Air + Magic Keyboardだけで十分だし、それがむしろ「今日は軽く書いてみようかな」という気分にフィットする。そのときの気分や目的に合わせて、「書ける自分」を引き出してくれる道具を選ぶ。それが僕のスタンスです。
だから僕にとって道具は、「これがなきゃダメ」な存在ではなく、「これがあると書けるかも」と思わせてくれる存在。ちょっと背中を押してくれる相棒、みたいな位置づけなんです。どれを使うかよりも、どう使うかが重要。
最近お気に入りのLogicool MX Mechanical Miniのレビューはこちら。小気味よい打鍵感とLogicoolの信頼性が相まって、ブログ・note執筆に欠かせない相棒となっています。
▶ MX Mechanical Miniを買ってみた。HHKBユーザーによるファーストインプレッション。


HHKB、自分に合わなければ売ればいいと思って試しに買ってみた結果、いつの間にか3年も使っていました。これ1年ほど前の記事なので、気がつけば4年も経ちました。すごい。

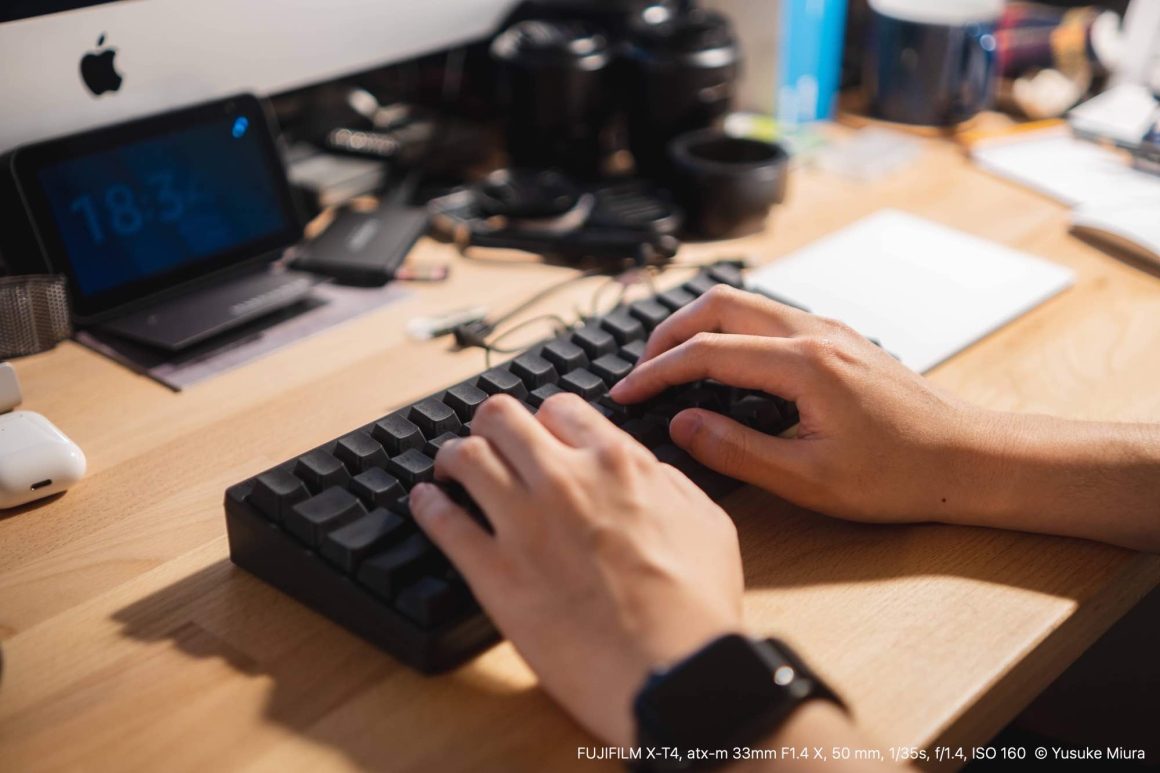
書くことに向き合う“スタンス”
ここまで書いてきたように、マシンも、キーボードも、カフェも、すべては「書ける自分」を引き出すための仕掛けです。でも結局のところ、どんな環境であっても、書くか書かないかを決めるのは自分自身なんですよね。書くことに向き合う「スタンス」こそが、一番の軸なんだと思います。
僕の場合、「書けるときに書く」のではなくて、「書くために自分をどう整えるか」を常に意識してきました。なぜなら、書けるときに書くスタンスだと、アウトプットの試行回数に限界がある。だから、多少無理をしてでも書ける自分を作り出すことができるように、努力をする。
気分が乗らない日でも、ほんの少しだけ整えてみる。お気に入りのマシンを開いてみる。コーヒーを淹れてみる。記事が仕上がるまで家に帰らない。そうやって「書く自分」を呼び戻していくうちに、気づけば自然と書けていた——そんな体験を何度もしてきました。
そして書くという行為は、誰かに見せるためだけのものではなくて、自分のための記録であり、自分と向き合う時間でもある。だからこそ、他人にどう見えるかを気にする前に、自分の気持ちや姿勢を整えることが大切なんだと思っています。
それに、完璧な文章なんて、たぶん一生書けないです。だから僕は、「完璧を目指すより、まず出す」ことを大事にしています。書きながら気づき、出してみて整えていく。そうやって続けることで、少しずつ自分の言葉が磨かれていくんじゃないかなと。
10年ブログを書いてきて、改めて思うのは、「気持ちが整えば、人は書ける」ということ。これからもたぶん、迷いながら、止まりながら、それでもまた書いていくと思います。そして、その「書き続ける自分」を支えるために、今日もまたコーヒーを淹れて、いつもの画面を開いているのです。
書く前に、まずは自分を整えよう
「書けないな」と思う日は、誰にだってあります。10年やっててもある。頻繁にある。そう思うたびに、自分のことを責めたくなるし、虚しくもなるんです。そして気づけば書けないことに焦っている。
でも、書けない自分を責めるより、書ける自分に戻す工夫を持っていた方が、ずっとラクに、そして自然に続けられる。このことに気づいてからは、書けない自分と向き合う時間が、辛くなくなったように思います。
気分を切り替える一杯のコーヒー。いつものキーボードの感触。ほんの少し場所を変えるだけでも、思考は軽くなる。それって全部、「書く前に、自分を整える」ための小さなスイッチなんですよね。
僕にとってのそのスイッチは、ここまで紹介してきたような環境や道具たちでした。きっと、誰にでも自分に合ったやり方があるはずです。
無理に気分を上げる必要はありません。うまく書こうとしなくてもいいんです。ただ、少しだけ自分に優しくしてみる。それが、また書き出すための最初の一歩になるのかもしれません。










