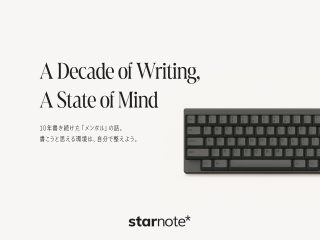難しく考えなくていい。
この記事には広告が含まれています。
「こんなこと書いても、誰の役にも立たないんじゃない?」
ブログやnoteを書いていると、脳内の慎重派がそんなことを言ってくる日もあります。確かに、旅の記録や日記のような記事を書いても、直接的に誰かの役に立つことはない。
でも、そのたびに自分の中で反論するんですよ。僕は書くこと自体を楽しんでいるし、思考と体験のアーカイブを作ることが目的なんだと。だから、誰かの役に立つことはモチベーションの源泉にはなり得ても、目的にはならない。そんなことを言い返しているんです。
つまり、自分が書きたいことを書く。ブログやnoteが「自分が書きたかったこと」で少しずつ埋め尽くされていく感覚を味わう。ただそれだけのことに楽しみを求めたって、いいじゃないですか。
その結果として、誰かにとって役に立ったり、新しい視点を提供できたり、おもしろいと思ってもらえる記事ができる。僕はそう信じているんです。自分自身が楽しまないと、本質的に役に立つことなんて書けないんですよ。
だから、発信とは「副産物」なんです。自分が楽しいことを突き詰めた先に、発信というゴールがある。それだけの話。

「ただキーボードが心地よい」でいい
僕は今この文章を書いています。当然だけど、自分でキーボードをカタカタとタイピングして、この文章をiPadに打ち込んでいるんです。そのモチベーションはどこにあるのか?
こんなこと言ったら驚かれるかもしれないけれど、この記事のテーマである「発信は副産物だ」という思考を書き出すことに、今の僕はモチベーションを感じていません。
それよりも、ただキーボードを叩きたい。最近気に入っているLogicool MX Mechanical Mini(茶軸)のカタカタと小気味よく文章を入力していく打鍵感を味わいたい。モチベーションはそこにあって、この文章を書いています。
つまり明らかに、今の僕の目的は「発信すること」ではないんですよ。真の目的は「お気に入りのキーボードを使うこと」や「キーボードの小気味よい打鍵感を味わうこと」であり、発信することはその結果として生じる副産物なんです。
でもいいじゃないですか。僕が気持ちよくキーボードを叩くことで、この文章が生み出されていっているわけで。副産物として脳内の思考を書き出すことに成功しているので、いいことしかありません。
日々の思考を書き留めた先に発信がある
とはいえ、ブログやnoteという場で文章を書く以上、思いついたことを何でも書いていいわけではありません。当然、誰かを傷つけるようなことは書いてはならないし、1ミリも誰かの役に立たないこと(たとえば、お腹空いたとか、会社の愚痴とか)を発信しても伝わらない。
そういう意味では、発信という手段に限らず、自分の内なる感情や思考を書き殴る場を持っておくといい。要するに日記やメモ。そこに書いた内容のうち、発信することに意味がありそうなことを深掘りして、記事の体裁に整えるといい。僕はそうしています。
どこかで書いたかもしれないけれど、僕はUlyssesという美しいテキストエディタで、日々の思考を書き出すようにしているんです。シンプルなUIのおかげで自分の思考とまっすぐに向き合えるし、Macや iPhone・iPadと状況や環境を選ばずに、忘れないうちに思考を書き留めることができます。
この記事も、もともとはUlyssesで書いていた思考をChatGPTと壁打ちして、Obsidianにまとめておいたネタが元になっています。それを読んだ上で新しく思いついた文章で書き始めているから、元ネタそのままじゃないんだけど、思考の起点はUlyssesに書き留めた文章。
これが結構本質のような気がしているんです。「決して誰にも見られることはない」という心理的安全性が担保された場所で、自分の思考とまっすぐに向き合う。その過程で、発信できそうな内容が出てきたら、その思考の欠片を拾い上げて、記事にまとめてみる。
そうやって自分と対話していき、記事という成果物にまとめて記録していく過程。これが楽しいから、僕はブログやnoteを続けているんだと思います。それ以上に今はこのキーボードの感覚の方が心地よいのだけれども。
いずれにせよ、こうして記事になっている思考は、何気なく書き留めた文章の中から抽出されたものなんですよね。だから、僕のUlyssesには日の目を見ない思考の欠片たちがたくさんあります。こうして思考を量産するからこそ、形になるアイデアが生まれてくるのかなーと思っています。
すなわち、実際の書き方にフォーカスしても、発信は副産物なんです。Ulyssesに思考を書き留め続けた結果、その抽出物として発信がある。

書くのは誰のため?
記事を仕上げるのはとてもとても時間がかかります。ひとつのテーマに対していろんな方向から書き上げていくと、だいたいいつも2,000〜3,000字くらいになってしまう。内容によっては5,000字を超えることもザラにある。そうなると、1本の記事を仕上げるために数時間はかかります。
僕も多くの人と同じようにフルタイムで働いており、基本的に時間はありません。だから、平日の終業後や休日に時間を見つけては、ちまちまとキーボードを叩いています。まさにこの記事も書き始めて2日目に突入。少しずつ進めています。
それでも、なぜ書くのか?
それは、自分のために書いているからです。2015年にブログを始めた当初から、一貫して自分のために文章を書いてきました。それは10年が経った今でも全く変わっていなくて、ひたすら自分のために「思考と体験のアーカイブ」を作り続けています。
それを公開することで誰かの役に立つこともあるかもしれないから、ブログやnoteで発信して「お裾分け」しているのです。このくらいのスタンスの方が、肩肘張らずに記事を書けると思っています。だからこそ10年も続けることができたのかなと。
つまり、自分のために文章を書き、その副産物として「発信」がある。そのくらいでいいんじゃないだろうか。

続かなくてもいい
僕が発信するのは、上にも書いたとおり「僕の思考や体験で役に立つものがあれば、お裾分けしたい」という想いからです。でも、このような、ある種の悟りを開いたようなスタンスに辿り着くまでは、一悶着ありました。
というのも、全然続かないんですよ。
書きたいと思っていても、何を書けばいいのか分からない。書きたい内容があっても、書く時間がなくて放置し、いつの間にか忘れている。そうやって離れているうちに、飽きてしまう。10年間を振り返ると、ただこのようなループを繰り返していただけだなーと思います。
特に、最初は記事(それも、今読み返せばめちゃめちゃ簡素な記事)を2本だけ書いて満足し、半年以上放置していたんです。確かにブログのことを思い出すタイミングもありました。でも、離れているうちにハードルがどんどん上がってしまって、書けなくなっていたんです。
今にして思えば、ただただ自分でハードルを上げていただけ。そして、時間を作るという発想がなかっただけ。書くことにも慣れていなかったし、発信することにも慣れていなかったから、余計にね。
でもまあ、そんな僕でも、気づけば10年も続いているのだから、何があるか分かりませんよ。明日の自分は書くモチベーションに満ち溢れているかもしれないから、書きたくない自分に強要する必要はありません。
だから、無理に続けようとしなくていいし、続かない自分を責める必要もないのです。これが大前提。でもちょっとだけ、気が向いたときに背伸びをしてみる日があると、そのあと見える世界はまた違ってくるかもしれませんよ。
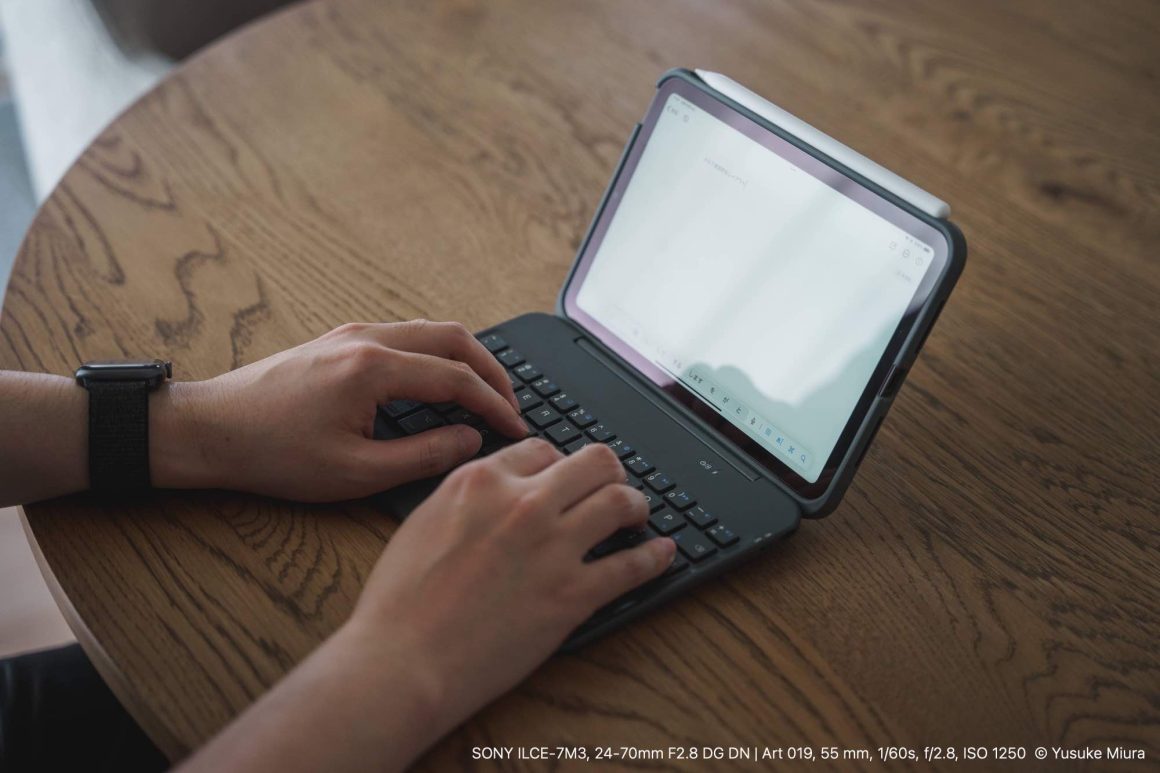
書くことをひたすら楽しもう
そして最も重要なのが、書くことを楽しむということ。だって、楽しくないと、続ける意味なくないですか?
楽しみ方はいろいろあると思います。文章で記録すること自体を楽しむ。頭の中のモヤモヤした思考が言語化されていく感覚を楽しむ。サムネイルを工夫して作るのを楽しむ。公開後の読者とのコミュニケーションを楽しむ。
僕の場合は、キーボードの打鍵感そのものを楽しんでいたり、真っ白なキャンバスからサムネイルを作ったり、読後感が残るように文章のテンポを調整したりするのも楽しい。
楽しいと思える瞬間がひとつでもあれば、それだけで書く理由になるんです。別に、誰かの役に立たなくてもいい。バズらなくてもいい。収益化なんてもっと後の話でいい。
「なんか気持ちよく書けたな」と思えたらそれだけで十分。書いた価値があると思っています。
書きたいから書く。発信は目的じゃない。
こうして改めて振り返ってみると、「発信したい」よりも先に「書きたい」があった方が、僕にとってはしっくりきていたんだと思います。
文章として世に出すことを最初から目的にしなくても、思いついたことを書き留めておくだけで十分。それが後に記事になったり、誰かの役に立ったりするかもしれない。でも、最初はそんなこと考えなくていい。
まずは、なんとなく書きたいと思ったときに、書いてみる。続かなくても気にしない。言葉にならなくてもいい。誰かに見せる前に、自分に見せるだけでいい。
そうやって、自分と向き合いながら書いた言葉の中に、いつか誰かに届くものがあるかもしれません。だから、焦らず、構えず、自分の「書きたい」に従ってみる。
それだけで、案外うまくいくものなんじゃないかなと思っています。発信は副産物でいいのだから。