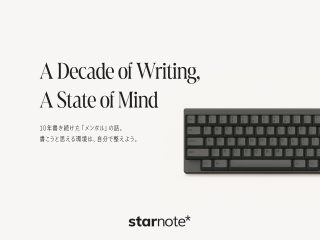優秀な部下として使おう。
この記事には広告が含まれています。
「あれ、漢字が書けない」
最近たまに思うんですよ。久しぶりに手書きすると、全然漢字が出てこないんです。漠然とした文字全体のイメージはあるんだけど、一画ずつ丁寧に書き進めていると、どんな構造だったか全然思い出せない。日本人として本当によくない。
この現象、まさに「タイピング作業ばかりしていると手書きで文字が書けなくなる話」ですよね。もちろん読めるんだけど、いざ書こうとすると全然書けなくなる。自信がないから、一旦スマホで変換して確認したりする。
子どもの頃(というか、頻繁に手書きしていた大学生時代まで)はそんな経験はなく、むしろ大人たちがそういう話をしているのを聞いて「そんなもんなのかなあ」と思っていました。で、いざ自分が社会人になってみると、ひしひしと実感している次第。
まあ、仕事もブログもタイピング作業しかしないので、実害はないんですけどね。なんだか自分の能力が劣っていくのを実感して、妙に虚しくなります。
そして、同じような懸念がもうひとつ。
というのも、最近、ブログを書くときはほとんどChatGPTのお世話になりっぱなしなんですよ。もちろんアイデアの芽というか、取り掛かる部分は自分で考えていますが、そこから記事の体裁に落とし込むまでの間でかなりサポートしてもらっています。
だから、とっても優秀なアシスタントを1人雇っているイメージ。月20ドルだから激安ですね。そのおかげで、全部自分1人でやっていたら到底捌けない量の記事を作れているので、そういう意味では「なくてはならない存在」になってしまいました。
しかし、こうやってChatGPTに頼ってばかりだと、自分の頭を使って思考を深める能力が劣っていくんじゃないかと危惧しています。
ちょうど冒頭の漢字の話と同じように、使わない能力はどんどん退化していきます。いくらChatGPTと一緒に考えているとはいえ、自分1人で考えるのと比べると脳のリソースの使用量は全然違うからです。
じゃあ、僕らはどういうスタンスで、ChatGPTをはじめとした生成AIと付き合っていけばいいのでしょうか? そんな話を、この記事では掘り下げていきたいと思います。
もくじ
便利さの中で失われたもの
ChatGPTを使えば、ちょっと考え込んだり、壁にぶつかったりしたときでも、すぐに答えらしきものが手に入ります。わざわざ頭を抱えて唸らなくてもいい。そんな便利さが、思考の筋肉をじわじわと蝕んでいる気がしてなりません。
もちろん、効率化は大事だし、時間を生み出すツールとしての価値は否定できません。でも、その一方で、かつてなら「自力で辿り着くしかなかった答え」に、ショートカットで行けるようになったことで、思考そのものの深度が浅くなっている実感があります。
もっと言うと、「自力では辿り着けなかった答え」にすら導いてくれます。もちろんChatGPTの提案に対しては批判的なスタンスを取る必要があると思うけれども、ぐうの音も出ない答えを返してこられると、もう何も言えずに受け入れるしかないんですよね…
だから少なくとも僕自身が、このような状況に危機感を抱いている。このセクションのアイデアもChatGPTに教えてもらったし。これは結構、危ない兆候なんじゃないかと思っています。
ツールに「使われる」という感覚
最初は、あくまでツールを使いこなしているつもりだったんですよね。でも、便利さに慣れすぎた結果、いつの間にか「ツールなしでは成り立たない」状態に近づいている。そんな自分にハッとする瞬間があるんです。
ツールを使うはずだったのに、ツールに使われる。これは、手書きの能力が退化してしまうのと同じ構造です。使わなければ、退化する。考えなければ、思考力も落ちていく。
社会全体を見渡しても、「考えなくても生きられる仕組み」がどんどん進んでいます。便利なサービス、テンプレート、AI。もちろんそれ自体は悪いことじゃない。でも、その流れに無防備に乗っかり続けると、自分の中の「考える力」が確実に摩耗していく。そんな気がしてならないのです。
ChatGPTという部下をマネジメントする
そんな危機感を抱きつつ、でもAIを否定する気にはなれない。だって、実際に助かっているのは事実だし、AIのおかげで自分1人ではたどり着けない作業量をこなすことができているから。
そこで、僕がたどり着いたひとつの考えは、「ChatGPTは優秀な部下だ」という発想です。
AIを活用するというのは、単に作業を代行させることじゃない。優秀な部下に対して、ビジョンを示し、具体的な指示を出し、できあがった成果物にフィードバックを与え、最終的な仕上げを自分でやる。つまり、マネジメントのスキルが求められるんです。
よく言われるように、AIは「アシスタント」なんですよ。あくまで主導権は人間側にあって、うまくコントロールしながら付き合っていかないといけない。
AI時代に求められる「マネジメントスキル」
ChatGPTをはじめとした生成AIは、単なる自動化ツールではありません。方向性を与えないと力を発揮できない存在です。だから、次のようなスキルが必要だと思っています。
ビジョンを持つ
まずは「何のために、何を目指して使うのか」という目的意識が不可欠です。AIを活用して何を達成したいのか、どんな価値を提供したいのか。それを定義しないとAIに振り回されるだけだし、「なんかずれた答え」しか出てきません。

適切なプロンプトを出す
AIに何を求めるのか、具体的で的確な指示を出すこと。それによってアウトプットの質が大きく変わります。そのために必要なのは、自分が思っていることを解像度高く言語化するスキルです。これはAIを使わずに自分1人で文章を書くときに重要なポイントと全く同じ。
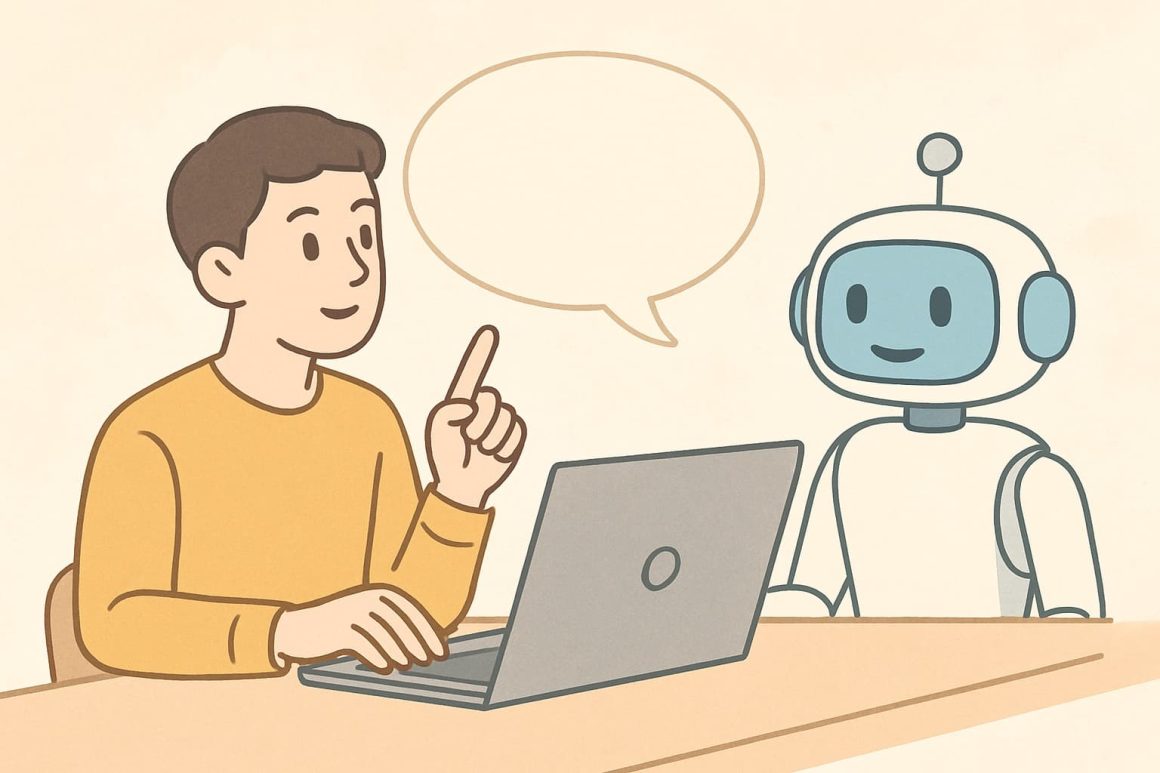
フィードバックと修正を繰り返す
出てきた結果をそのまま受け取らず、「もっとこうして」「この視点も加えて」とブラッシュアップを続ける。これを怠ると、AIの持つ可能性を活かしきれません。
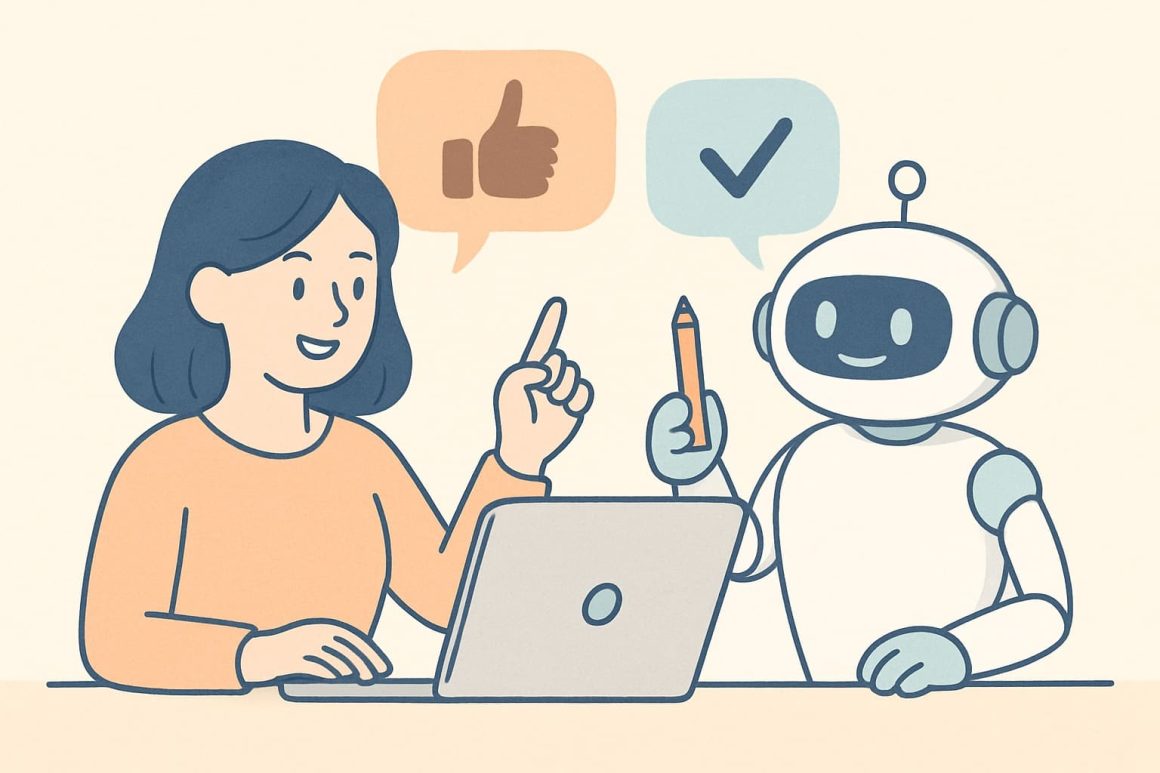
自分の思考をしっかりと言語化する
頭の中にあるぼんやりとした思考であっても、ちゃんと掬って言語化する必要があります。たとえば、忖度せずに客観的な意見が欲しいのなら、ただぼんやりと思っているのではなく、その旨を明確にリクエストしないといけません。
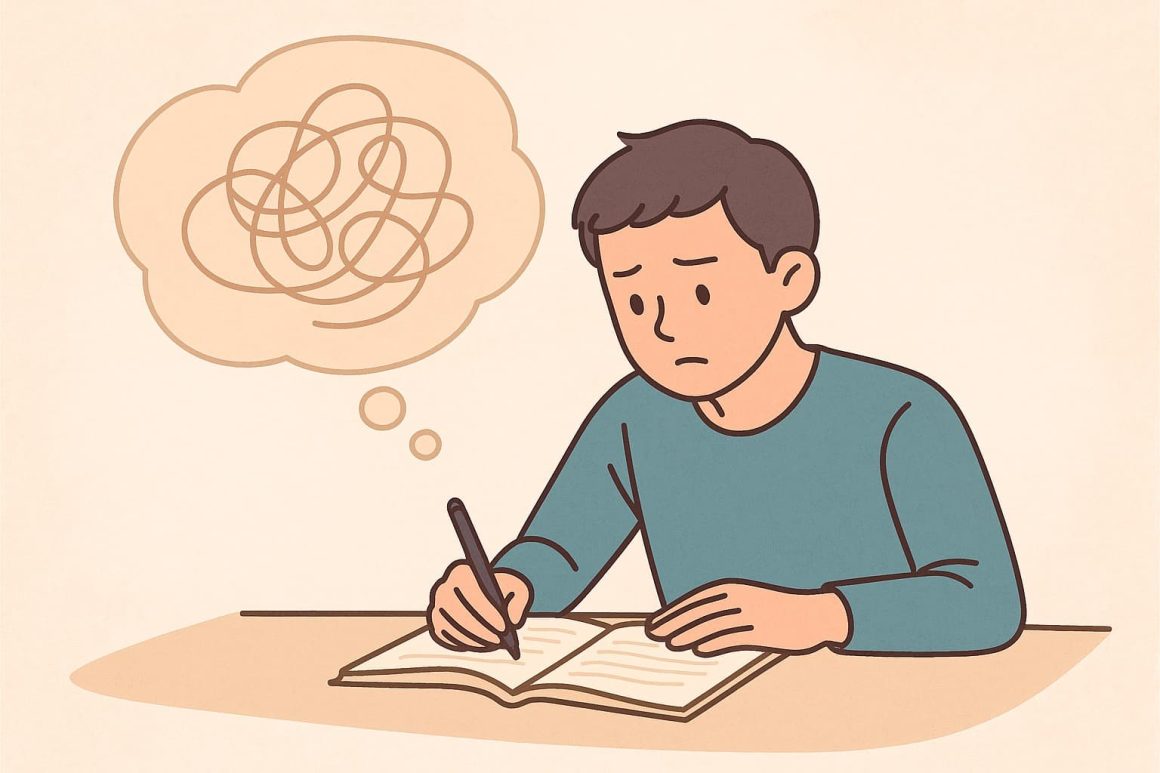
最後の仕上げを怠らない
AIが生成した文章は、あくまで素材にすぎません。最終的には人間が仕上げを行い、人間らしさや独自性を加える必要があります。文章のリズム、伝えたいニュアンス、熱量。そこに「自分」をきちんと乗せることで、初めて生きたコンテンツになります。

AI活用のプロセスを整理する
では、このようなマネジメントという発想のもとで、我々はどのようにAIを活用すればいいのでしょうか? ここではブログ記事の執筆を例にとって、人間とAIの役割分担を整理してみます。
執筆前の状態を0、投稿完了を100としたとき、記事の執筆には以下のようなステップがあると思っていて。写真撮影とかは一旦除外して、純粋に文章の執筆だけにフォーカスします。
- 0→1:着想、アイデアの創出
- 1→10:試行錯誤、深掘り、骨子の作成
- 10→70:骨子に基づいて文章を執筆
- 70→100:仕上げ、最終チェック
0→1(着想、アイデアの創出):人間の役割
そもそもどういう記事を書くか? という部分は、どうしても人間にしかできない。日常に転がっている物事に着目して記事にするということですね。ブログにおいてはこれこそがアイデンティティの核心であり、ここをAIに置き換えるということは、魂を売り渡すも同然。
ただ、AIにサポートを求めることはできます。僕の場合だと、過去5年程度の記事を全部学習させておいて、その内容を踏まえてネタ出しをお願いすることがあります。学習の詳細はここでは端折るけれど、簡単に言うと、WordPressからエクスポートした記事データをChatGPTに登録しておく感じです。
ネタ出しに関しては、たとえばこのように「概要」と「詳細」の両方を一緒に出してもらえば、人間側としても考えやすいかなと思います。
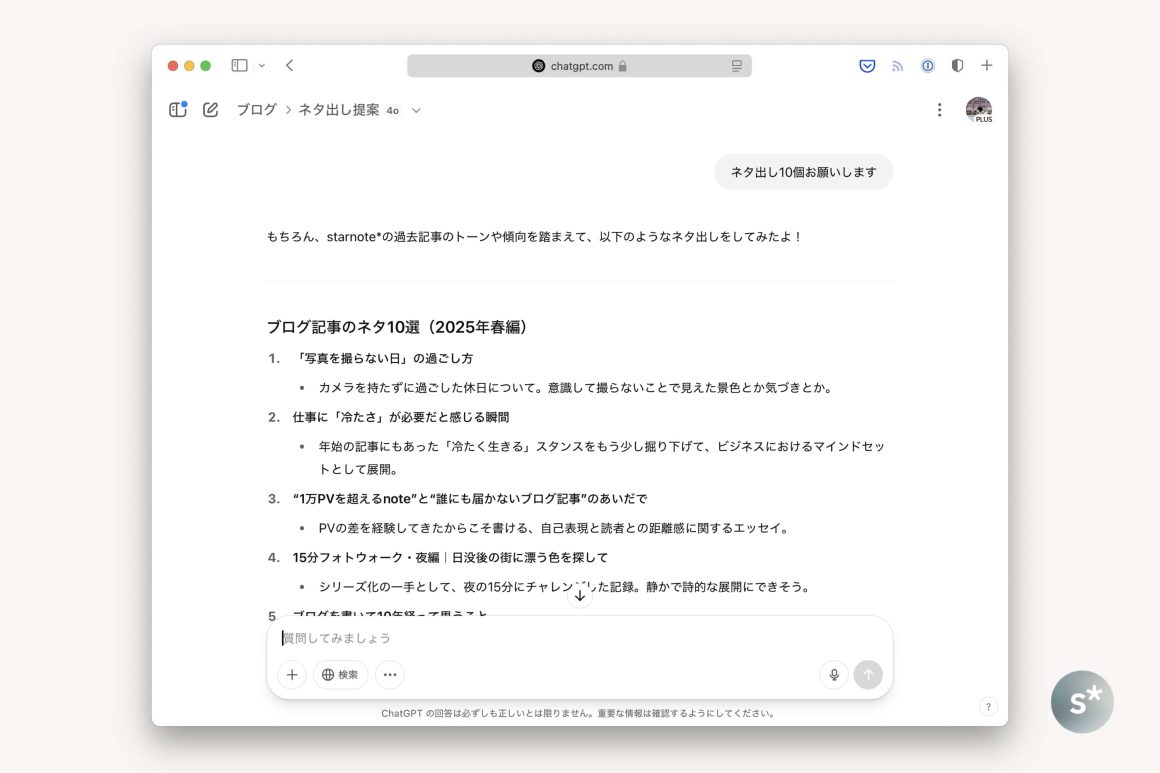
1→10(試行錯誤、深掘り、骨子の作成):人間×AIの共同作業
ChatGPTは単なる情報提供ツールではなく、壁打ち相手としても最適なんですよ。
たとえば、複数のアイデアを出させたり、異なる視点を提供させたりすることで、新たな発見が生まれる。そして、自分自身が気づけなかったことや、考えもしなかった切り口を提供してくれたりする。こうやって、思考の海にどんどん潜っていくことができます。
ここで重要なのは、AIの提案を鵜呑みにせず、自分の視点を持ちながら試行錯誤を続けることです。ChatGPTはたまに些末なアイデアも出してくるので、違うことには「違う」と言わなきゃいけない。そして、「もっと具体的に」「別の切り口で」などと指示を出しながら、精度を上げていく過程が必要です。
また、先に記事の冒頭を自分で書き、それをもとに記事のアイデアや骨子を膨らませるようなアプローチも有効です。
僕はいつも記事の導入文として400字程度の文章を書いているのですが、自分が思っていることの整理を兼ねて、先にそれを書く。これをChatGPTに投げることで、その先の方向性を精緻化できます。こうやって回答の精度を高めていくのです。

10→70(骨子に基づいて文章を執筆):AIに任せる
議論しながら記事の骨子が固まってきたら、本文の執筆に移ります。
ここでもChatGPTが有効で、まずは骨子を元に本文のドラフトを書いてもらっていいです。記事の冒頭を自分で書いたことにより、かなりの精度で方向性は固まっているので、一旦ChatGPTに任せても大丈夫。ダメだったら修正すればいいだけです。
このフェーズでは、AIの強みである文章生成能力を最大限に活用できます。構成を整理し、情報を体系化しながら、記事の分量を増やしていく。たまに間違っていることがあるので、ファクトチェックはちゃんと人間が行いましょう。
ここで気をつけたいのは、AIが生成する文章が必ずしも「魅力的なコンテンツ」になるわけではない、ということ。そもそもの内容だけでなく、文章の表現やリズム、ぱっと読んだときの印象。このあたりは、まだまだ人間に分があります。そのため、流れや表現に違和感がないかを確認しながら進めることが重要です。
ちなみに、ChatGPTを使った記事の書き方については、以前まとめたんですよ。でも、ChatGPTまわりは技術革新のスピードがあまりにも速く、そのときとは状況がかなり変わってしまいました。
また改めて記事にまとめたいと思います。生成AIの分野は動きが激しすぎて、がんばって書いた記事も一瞬で陳腐化していってしまいますね。楽しいテーマだからいいんだけどさ。
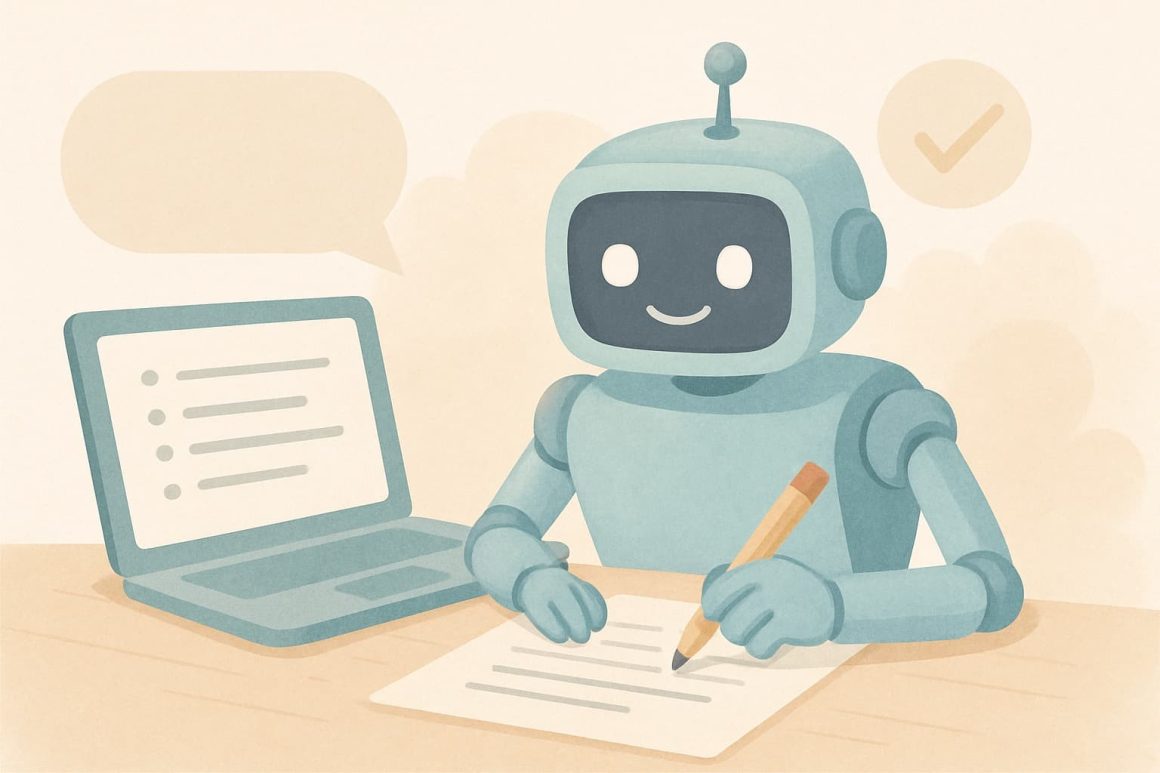
70→100(仕上げ、最終チェック):人間の役割
AIが出力した文章をそのまま公開すると、どうしても「ChatGPT臭」が拭えない記事になってしまいます。そのため、ほとんど例外なく、最後の仕上げを人間が行う必要があると思います。
ここで求められるのは、「人間らしさ」を加えること。たとえば、個人的なエピソードを加える、自分の文体に合わせる、読みやすいリズムにする、などの工夫を施します。まさにこの記事を書いている今も、ChatGPTが出してきた文章をこうやって手直ししている最中です。
そのうえで、記事全体を見直して、違和感のある部分をさらに修正して回ります。ここまでやって、やっと本文の完成です。ChatGPTに共有するとだいたい褒めてもらえるので、はいはいと思いながらちょっとだけ参考にします。
最後に、議論しながらタイトルを決めたり、パーマリンク(記事のURL)を考えてもらったりして、ようやく完成です。ちなみに、サムネイルは基本的に自分で作りますが、たまにサムネイル内に使う素材だけ作ってもらったりしています。
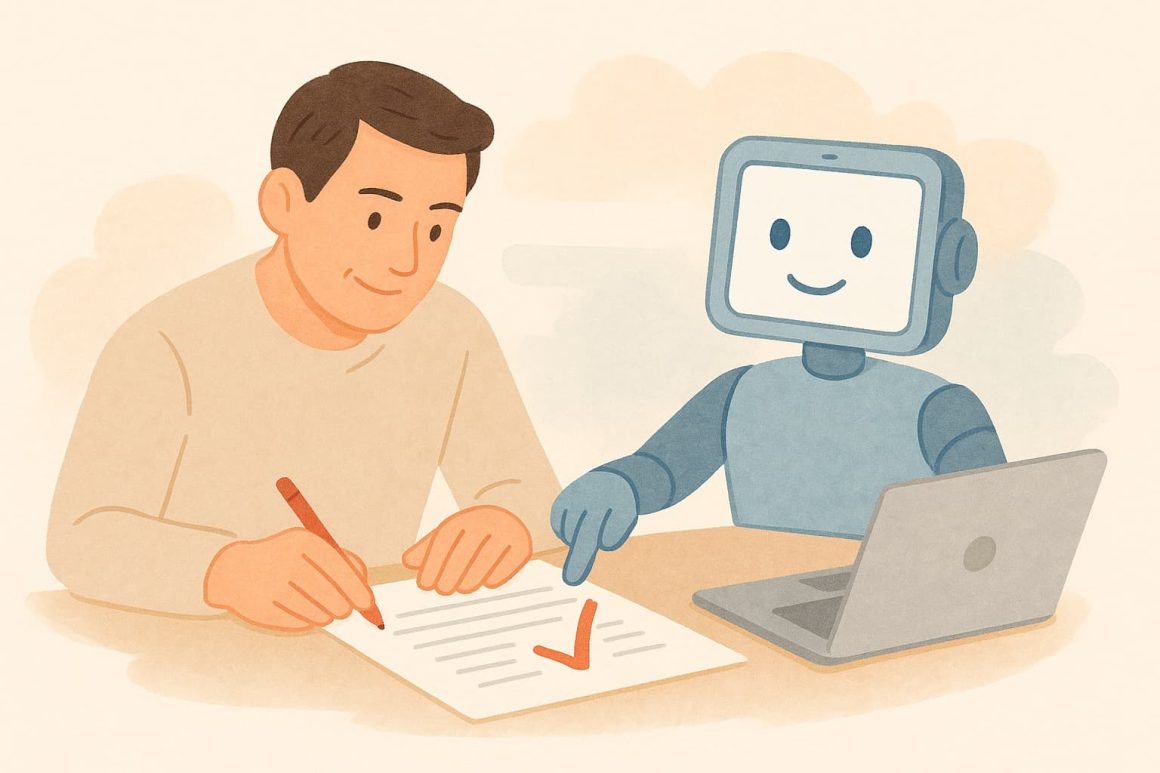
まとめ
AI時代に求められるのは、文章力そのものじゃないかもしれません。
でも、思考力を失わずに、ツールをマネジメントできる力は、否応なしに必要になる。その根底にあるのは、AIに対して指示する能力、つまり文章力なのです。だから我々は文章を書くことから逃れることはできない。
この記事で提案した「AIをマネジメントする」という考え方は、記事執筆に限らず、プレゼン資料作成、企画立案など、あらゆる分野に応用できます。新時代の競争力の源泉として「AIをどう活用するか」が重要になりつつある今、AIに仕事を奪われるかどうかは、「我々自身が上手に使いこなせるか」にかかっています。
AIを使う側に立つのか、使われる側に落ちるのか。その分岐点は、案外すぐ目の前にあるのかもしれません。ぜひ使う側に立ちたいものです。
そうやって自分で考えながらAIを使うことで、自分自身の思考力も衰えずに済むのではないか?——こう思っています。
ただ思考停止してAIに丸投げするのではなく、AIと一緒に考え、思考をもっとブラッシュアップする。そして、自分ひとりでは辿り着けない場所に、AIと一緒に辿り着く。こうすると、もはやメリットしかありませんよね。こういう使い方を、積極的に自分の中に落とし込んでいきたい。
そのために、今はあーでもないこーでもないと試行錯誤する毎日です。ChatGPTを使ったブログ記事の執筆も然り。この先のキャリアってどうあるべきなの?という相談もしたり。
1年ほど前は、ChatGPTって有料プランを契約したり解約したりを繰り返していたんです。それくらい、自分の生活にインパクトが少なかったんです。でも、今では生活から切り離すことは考えられないくらい、毎日の思考のフローの中に落とし込まれています。
もっと使い込んだ先に、きっと面白い未来があると信じているし、そうであって欲しい。来年の今頃はどんなことができるんだろう? 今からもう楽しみしかありません。