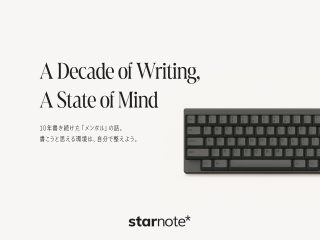薬学部を出たら薬剤師にならないといけない?
この記事には広告が含まれています。
薬剤師として病院や薬局で働く。
それが当たり前のように目の前に提示されていた6年制薬学部の後半、その実習の場で、僕はずっとモヤモヤしていたんです。「なんか違う」と。
その違和感の正体が分からないまま、とりあえず実習をこなしました。進路を考えるタイミングでは、大学院に進んで研究をこなし、博士号の取得を目指すという選択をしました。けれども、その「なんか違う」は、ずっと僕の中に残っていました。
それから10年以上が経った今、粗々な解像度だった「なんか違う」を、もう少し深掘りしてみようと思いました。今だったらできそうな気がしている。
そもそも自分誰やねん?という疑問については、こちらの自己紹介記事が詳しいです。僕のこれまでの歩みと、今やっていることについて書きました。
▶ あらためて、自己紹介を。ちゃんと書くのは初めてかもしれません。
読むのが面倒な人のために、ざっくり言うとこんな感じです。
- 国立大学薬学部(6年制)卒業[薬剤師免許]
- 大学院博士課程修了[博士(薬学)]
- 新卒でPMDA(医薬品医療機器総合機構)に入社
- 新薬審査・治験相談を担当(中枢神経・眼科・麻酔領域)
- 現在:医療IT企業で事業開発/プロダクト企画に従事
- 医療のデジタル化・制度設計・プロダクト開発の上流工程を担当
- 10年ほど個人ブログ「starnote*」を運営中
「患者さんのために」がピンとこなかった
多くの薬学生が口にする「患者さんのために働きたい」。その気持ちはよく分かります。僕もそう思います。
でも、臨床現場というレイヤーにおいて、僕はそこにリアリティを感じられなかったんです。もっと言えば、目の前の患者さんが元気になったとしても、正直、それが自分にとってのモチベーションにはならないと思えてしまった。これは冷たい話に聞こえるかもしれないけれど、当時の僕にとっては切実な感情でした。
もう少し普遍的な表現にすると、「自分の仕事によって、誰かが健康になったり、命が助かったりするということに対して、〈自分ごと〉として感じることができなかった」と言うことができるかもしれません。
患者さんと直接接することで、その患者さんが健康になっていくのを目の当たりにすれば、もちろん嬉しいです。手術が成功した人工股関節置換術の患者さんと一緒に喜んだり、ワーファリン手帳を拝見してPT-INRが綿密にコントロールされていることに感動したり。個々の患者さんに着目すると、医療者としての使命を感じることはありました。
けれども、このような薬剤師としての仕事をずっとやっていくことを想像したとき、僕は一体、何をモチベーションにすればいいんだろう?——実習当時の僕はこう思っていました。
そもそも、僕は現場で何かを処理し続けること自体、あまり得意じゃないんです。目の前の人に即座に対応することよりも、全体の仕組みを最適化したり、問題が起こっている背景を考えることの方に興味が向いてしまう。
そういう意味では、ずっと現場に身を置き続ける働き方には向いていない。当時から漠然とそういうことを思っていました。だからこそ、臨床現場に残る判断をしなかった。でも、その判断が正しかったのかどうか、ずっと頭の片隅で考えてきたんです。
転機が訪れたのはここ数年。最近流行っているMBTIという性格診断をやってみると、過去の思考を見事に裏付けるように「INTJ:建築家」なんですよね。
このタイプは、独創的かつ戦略的にものごとを考える傾向があり、あらゆる状況に備えて計画を立てるということで、過去の自分の判断が腑に落ちた気がしました。であるからこそ、現場で処理を積み重ねる仕事よりも、仕組みや構造を設計する側にいる方が自然だったのだと思います。
要するに、患者さんと接することにモチベーションを感じないというのは、冷たいとか逃げではなく、「貢献の仕方が違う」だけだった。今はこのように思っています。
接することだけが貢献なのか?
実習では、患者さんとの接点が仕事の中心にあります。患者さんを中心に据え、患者さんが主体になって、コメディカルが治療をサポートする。このコンセプトには共感するし、現場というレイヤーでは最適でしょう。
でも、それを自分の中に落とし込んだときに、どうしても「このやり方でしか医療に関われないのか?」という問いが頭から離れなかったのです。
薬剤師の仕事には敬意を持っているし、必要不可欠な職業だと思います。でも、自分がそこに入っていくイメージが、どうしても描けなかった。イメージできないものはしょうがない。それゆえに、僕には薬剤師として働くのは向いてないのだと悟りました。
医療に貢献する方法は、必ずしも「患者さんと接する」ことだけではありません。薬学生の進路としてよく言われるけれど、薬剤師として働く以外にも、製薬企業で研究職・開発職・MRなどとして働いたり、行政機関で働くような選択肢もあります。
患者さんに医療を提供する臨床現場を起点として考えたとき、薬を開発するような製薬企業はそれより上の工程(つまり「上流」)にあります。また、日本の医療の仕組みや在り方を考える国やコンサル企業は、さらに上流にいると考えることができる。
このような上流の仕組み側に回ることで、より多くの患者さんにインパクトを与えることができるのではないかと、当時から感じていました。
現場では一人の薬剤師として目の前の患者さんと向き合う。一方で、制度や技術、仕組みを整える側に回ると、その先にいる数万人、数百万人に影響を与えることもできる。それこそが、自分にできる本当の貢献の形かもしれない。そう考えるようになったのです。
患者さん一人ひとりに丁寧に対応することは素晴らしい。でも、僕は構造のほうに手を伸ばしたい。現場での実習は、そう気づくきっかけになりました。
自分の経歴をとことん尖らせればいい
じゃあ、そのためには何が必要だろうか? 自分に足りないのは何だろうか?
たぶん気づくのが遅かったんですよね。大学に入学してすぐに気づくことができれば、もう少し動きようがあったかもしれません。
というのは、このような上流の工程に関わることができる人って、現場と比べてかなり少ないのです。限られた人しか関わることができないから、選ばれるに相応しい経験が必要だし、本人のポテンシャルもシビアに評価される。
そう考えたとき、もっと尖った人材になる必要があると考えました。6年間の大学を卒業してから社会に出ても、よくいる普通の薬剤師ですよ。でも、卒業後に大学院にまで進学して博士号を取れば、それだけでかなり尖らせることができます。
このように考えて、大学院に進学するという選択をしました。
大学院で研究を行う以上、ある程度研究に対して興味関心がなければ、完走することはできない。このような興味関心が人と比べて大きかったか?と問われると否定するけれども、少なくとも完走できるだけの興味関心を持っていたのかもしれませんね。当時は全然興味ないと思っていたけれども。
それはなぜか?と今になって考えてみると、少なくとも「自分の中から湧いてくる問い」を解いていく方が、ずっと熱量を持てるんですよ。薬剤師として患者さんと向き合っても、いくら薬について造詣を深めても、なかなか自分ごと化できなかった。けれども、大学院の研究は自分ごと化できた。それだけのことです。
実際にどのような研究を行ってきたか?については、別の機会に改めて。ざっくり説明すると、薬物送達(DDS)の分野で、脳に対する外部刺激応答性の薬物送達について研究していました。
仕組み側に立って、経歴を掛け合わせる
その後のキャリアでPMDA(医薬品医療機器総合機構)に入り、さらには医療IT企業へ。振り返ってみれば、それはすべて「仕組み側に立つ」ためのステップだったように思います。
果たして本当に仕組みを作れているのか?と自問自答する場面も、もちろんあります。でも、まさしく今も全国規模で使われるシステムの開発や運営に携わっているし、現場で医療を実行する土台を作っています。これって、医療に十分貢献できていると言うことができると思うんです。
だから、必ずしも臨床現場が全てではない。現場で患者さんと接することができなくても、制度を設計し、技術を届ける側に回ることで、確実に医療に貢献できる。しかし、臨床現場から抜け出すためには、薬剤師という武器だけでは、ちょっと少ないかもしれない。
上でも書いたけれど、薬学部を卒業しただけでは、薬剤師という武器しか持っていないんです。でも、大学院を修了すると、そこに博士号が加わる。その後、PMDAにおける新薬審査の経験や、IT企業における医療機器プログラム(SaMD)に関する事業開発・プロダクトマネージャー(PdM)の経験が加わったわけですよ。
つまり、今の僕は「薬剤師 × 博士 × 規制当局 × SaMD PdM」という経歴を掛け合わせた上に立っています。最近転職エージェントと話していても、ここまで希少価値のある人は少ないようだし、これができたのは僕がこれまで戦略的に経歴を掛け合わせてきたからに他なりません。
今いる場所から考えてみても、僕にはこのポジションのほうが向いていたように思っています。薬学生だからといって薬剤師にならないといけないわけじゃない。薬剤師以外の道もあるんだよ、ということを声を大にして伝えたいのです。
違和感は「場所が違った」というサインだった
あのときの違和感は、「自分には向いていない場所だよ」というサインだったのかもしれません。
これは決して逃げではなく、単に自分の適性に合う場所ではないというだけです。むしろ「6年制薬学部を出たから薬剤師にならないといけない」という考えの方が凝り固まっています。そう思ったときは、もう少し薬学以外の分野にも目を向けた方がいい。
そして今、自分の内側から湧いてくる問いに向き合える環境で働いている。それはすごく幸せなことだと思います。薬剤師にならなくても、薬学部で学んだことは確実に生きている。大学院で培ってきた論理的思考力もしっかりと生きている。
「そんな生き方もあるんだよ」「むしろこっちが楽しいよ」と、あの頃の僕に伝えてあげたいです。そして、最後まで読んでいただきありがとうございます。少しでもヒントになれば嬉しいです。