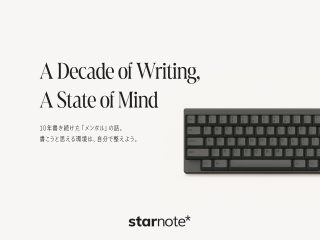どこにあるかな?
この記事には広告が含まれています。
僕は、何でもできるMac(iMacやMacBook Air)と向き合って作業をこなしています。ブログを書いたり、写真を現像したり、企画のメモを書き出したり──僕の創作活動のほとんどはMacの前で完結するのです。
Macで作業するのはとても快適だし、便利なツールが集まっているから、クリエイターの端くれとしては恵まれた環境だと思っています。でも——
- ブログを書こうと思ってMacを開いたのに、気づけばYouTubeを見ていた。
- 写真を現像しようとしたのに、なぜか昔の写真を眺めて思い出に浸っていた。
こんなことだって発生します。
つまり、「何でもできる」ということは、文字通り「何でもできる」ということなのです。やるべきことよりも、ついやりたくなることに手を出してしまう。誘惑に満ちた広場にひとり放り出されているような感覚。
もちろん、自制心を持てばいいという話かもしれません。でも人間はそんなに強くない。特に「やる気が出ない」ときには、つい楽な方に流れてしまうのですよ。悲しいね。
単機能デバイスと、でも万能じゃない
この問題に直面したとき、「じゃあ、何でもできるマシンを使わなければいいのでは?」という発想も浮かびました。たとえば文章執筆専用のデバイスとして有名な「ポメラ」。ネットも通知もない。文章を書くことに集中できる。
ただ、なんか引っかかっていて。
僕がやりたいのは、文章を書くことだけじゃないんですよね。ブログ・note記事の場合だと、写真を貼ったり、サムネを作ったり、文章の体裁を整えたり、やることはいろいろあります。文章を書くのはあくまでも一部で、もっと幅広い工程があるんです。
たしかにポメラなら文章は書ける。でも、それ以外はMacに戻らないとできない。行ったり来たりするうちに集中力が途切れてしまう。だったら最初からMacで完結させた方がスムーズでしょう。そう思ってずっとMacを中心とした作業環境を構築してきたんです。
だから結局、「何でもできるMacで、どうやって集中するか」に立ち返ることにしました。
小手先の仕組み化よりも、モチベーションを呼び起こそう
これまで、いろんな仕組みを試してきました。
ポモドーロアプリの導入、タイムブロッキング、通知オフ、集中モード。でもこれらは小手先の仕組みであって、「やる気があるとき」には効果的でも、「そもそもやる気がないとき」には何の意味も持たないんですよ。無視しようと思えば無視できちゃうからね。
だからこそ、このような小手先の仕組み化よりも大事にしたいのは、「モチベーション」。つまり、やる気そのものをどうやって呼び起こすか。一度心の中にやる気が生まれてしまうと、それを取り除くことは極めて困難です。それを逆手に取ります。
ここに着目して、自分の感情や行動を観察してみると、いくつかのスイッチが浮かび上がってきました。
自分の“やる気スイッチ”を探る
僕の場合は、以下の場合にやる気スイッチがオンになるように思っています。そして、このような状態に自分自身を意識的に入れ込むことで、再現性高くやる気スイッチをオンにすることができています。
- 素晴らしいアウトプットに触れたとき
- キーボードの打鍵感を楽しみたいとき
- アイデアが溢れてきたとき
- 無理矢理書いた文章が意外とよかったとき
- 人の少ないスタバで作業しているとき
1. 素晴らしいアウトプットに触れたとき
誰かのブログ、動画、本──ジャンルはなんでもいいけど、「うわ、すごい…自分もこんなふうに表現したい!」と思えるアウトプットに出会うと、無性に自分も何かを作りたくなります。作品に触れて、心がざわつく。そのざわつきが、強い衝動となってキーボードを叩かせる。
対策
意識的に、自分の「モチベの源泉」となるようなアウトプットに触れる習慣をつくる。YouTubeの「モチベ上がる動画」プレイリストを作っておくのもいいし、「モチベ上がる記事リスト」を作ってもいい。情報の消費を、意図的に燃料にするイメージ。
2. キーボードの打鍵感を楽しみたいとき
これは身体的な欲求に近いです。内容はどうでもよくて、とにかくキーボードで何かを打ちたい。指がうずく感じ。タイピングそのものの楽しさを原動力として、アウトプットという歯車を回す。
対策
自分が気に入っているキーボードを常にすぐ使えるようにしておく。僕の場合は、HHKBとMX Mechanical Mini。書く理由が「書きたいから」じゃなくて、「打ちたいから」でもいいと思っています。環境を整えておくだけで、自然と「ちょっと書いてみるか」の流れに持ち込めます。
3. アイデアが溢れてきたとき
何かをきっかけに、次から次へとアイデアが湧いてくる状態。思考が止まらなくて、手を動かさないと追いつかない。それを逃さないために、自然とキーボードに向かう。
対策
この状態は、前述の「1. アウトプットに触れる」→「2. 打鍵でウォームアップする」を経て誘発されることが多い。だから、1と2を組み合わせるのが効果的。先に動き始めると、自然と脳が活性化されてこの状態になる気がします。
4. 無理矢理書いた文章が意外とよかったとき
気が乗らないけど、とりあえず5分だけ書いてみる。そうすると、不思議と手が動き、意外と面白いアイデアが出てくることがあるんです。思考が整理されて、「あれ、もう少し書いてみようかな」と思えます。
対策
「5分だけやってみる」でいいし、なんなら最初の取っかかりは「1分間ひたすら何かを書く」でも全然OK。最終的にオーバーしても全然いいから、時間を区切ることで取り掛かるハードルを低くして、とにかく書き始める。内容はどうでもいい。iPhoneでもいいし、ベッドの中でもOK。何も思いつかなくても、キーボードを叩き続ける。形式よりも勢いが大事。
5. 人の少ないスタバで作業しているとき
カフェの適度なざわめきと、周囲の視線。作業しなきゃという軽いプレッシャー。これがいい方向に働いて、集中モードに入れることがある。
対策
自分の「集中できるカフェ」をいくつかリストアップしておく。首都圏だと理想的なスタバはなかなか少ないけれど、平日夜間のロードサイド店など、穴場などを開拓しておくといい。場所に強制力を持たせるのも一つの手です。
結論:モチベーションは、「起動」できる
まとめると、「やる気があるときにやる」のではなく、「やる気が出る状態に自分を持っていく」ことが大切でした。
- モチベをくれる作品に触れる
- キーボードを目の前に置く
- 5分だけ書いてみる
- 作業カフェに行く
こういった行動は、すべてスイッチになります。そしてそれらは、習慣にできます。断言します。「やる気」は仕組みをもとに作り出すことができます。
もちろん、うまくいかない日もあります。うまく書けない日もあります。それでも、何も考えずにただ待つよりは、自分で自分のスイッチを押す努力をした方が、確実に前に進めると思うのです。そういうときはChatGPTの力を借りても、もちろんいい。
「何もやる気が出ない」と思ったときこそ、その感情を放置せず、観察し、仕組みに変えていく。それが、自分のモチベーションと付き合ういちばんの近道なんじゃないかと思います。