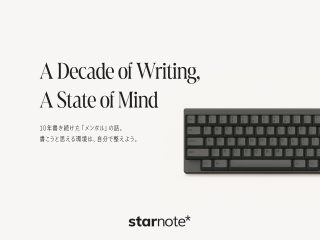深いところから生まれてくる。
この記事には広告が含まれています。
僕は、ブログやnoteで発信を続けてきました。もちろん書くこと自体は好きなんだけど、実は、運営における全ての工程を心地よくこなせるかと言われると、そうでもありません。
たとえばネタ出し。苦しいよね。よくぶち当たる壁です。
「何を書けばいいのか?」と考え始めると、急に息苦しくなり、数日迷い続けることもあります。でも、記事を書くことが目的になってはいけないし、どうせ書くなら、自分が本当に語りたいと思えるテーマを選びたい。
でも、その「語りたいもの」がなかなか見つからない。そうやっているうちに、視野がどんどん狭くなっていく。
そんなときに僕がいつも立ち返るのが、もっと前段階の「人生観」みたいなものです。自分が何を大事にして生きているのか。どんな方向を向きたいのか。そこが整うと、不思議とネタ出しの迷いも減ってくる。
人生観とは、自分を覆い尽くすとても巨大なもので、その上に「どんな仕事をしたいか」「家を買うかどうか」「どんな暮らしを理想とするか」など、いろいろな思想が乗っかってきます。
だから、前に進むためには、自分の人生観を信頼して、ひたすら信じた道を進むことしかできないと思っていて。それが合ってたって間違ってたって、どっちでもいいじゃないかと。そんなスタンスでこれまで生きてきました。
「のらりくらり」じゃ越えられなかった壁
これまでの自分を思い返してみると、バランス感覚でもって「のらりくらり」とやってきたところもあれば、ちゃんと腰を据えて取り組まないとクリアできないハードルもあったりして、割といろんな困難を乗り越えてきた気がしています。
たとえば、博士課程で研究の道を究めてきた経験。論文という形で未知なものを明らかにし、世界の果てに旗を立ててきた。これは、思っていた以上に一筋縄に行かなかったなと思っていて、腰を据えて真っ直ぐに取り組んだ経験のひとつ。
その結果として、自分の思考に深みが生まれたことは間違いないし、表面的な部分に着目しても「博士号」という誰の目に見ても明らかな肩書きを手に入れました。
そのような経験の前提に立ち返ってみると、未来が見通せない中で、自分の4年間を捧げるというリスクを取り、博士課程に進学したわけです。正直、心の底から不安で不安で仕方なかった。
でも、そういうときに自信喪失してしまったら、成果なんて上がらない。自分の心と体を健康に整え、不安なんて遠くに蹴飛ばして、腹を括って進むしかないでしょう。目の前の暗闇に向かってひたすら道を開拓していく。それが人生というものです。
だって、社会人となった今だって同じことをやってるんですよ。会社の中で進めているプロジェクトにすら、正解はない。みんなの合意のもとで意思決定をして、道を切り開いていく。
さらに、来年自分がどんな仕事をしているかなんて分からない。今の会社で順当に働いているかもしれないし、もしかしたら転職しているかもしれない。はたまた、起業して社長をやっている可能性だってゼロじゃない。
その道は、毎日の自分の選択の果てにあるものであって、まさに誰もが道を切り開いていくサバイバーなんです。まずはそれを自覚したい。
読まれなくても書き続けられる理由
発信を続けていると、必ずぶつかる壁があります。たとえばブログやnoteで発信していて、誰にも読んでもらえないとしましょう。
そのときの気持ちって、「自分には発信するセンスがないんじゃないか」とか、「自分の経験なんて誰の役にも立たないんじゃないか」とか、「誰にも読んでもらえない文章を書くのが辛くなってきた」とか、そんな感じでしょう?
いやいや、これだって同じことですよ。誰もがゼロの状態から始めている。もちろん、それ以前に別の場所で信用貯金があった人は伸びるのが早いのだけれど、最初がゼロであることは同じです。そして、誰もが「記事を出す」という形で、自ら道を切り開いているんです。まずはこれを理解したい。
ではなぜ、次々と記事を書き続けることができるのか? それは、
自分の中に書きたいものがあり、かつ、それを書いていくことが正しいと信じているから
に収束する。
正しいと信じることができれば、モチベーションは上がる。モチベーションが上がれば、数をこなすことが苦じゃなくなる。そうなると既に量産フェーズです。道を切り開いていくことが楽しくなってきます。
量産フェーズに入ると、急に世界が明るく見える瞬間があります。たとえ多くの人に読んでもらえなくても、書くこと自体に満足感が生まれる。だから、書くことに対して「構える」必要がなくなる。肩の力が抜けて、生活の中のちょっとした違和感や発見が、全部ネタに変わっていく。
この状態はすごく強くて、「書くための生活」じゃなく、「生活するだけで勝手にネタが生まれる」という思考回路ができあがります。一度ここまで来ると、もう後戻りしないし、する必要もない。むしろ、書かずにいるほうが落ち着かなくなるくらいです。
このような状態に自分を持って行くことができると、気づけば記事が量産されている。そうすると、自ずと多くの人に読まれるようになる。ニワトリと卵の話じゃないけど、記事を量産しないことには、そもそも読んでもらえるきっかけすら生まれません。
書く力は、内側の安定が作るものである
少し一般化してみると、
- 暗闇の中に道を開いていくことを楽しむマインドを身につける
- そのようなマインドが礎となり、周囲の反応を気にせずに書きたいことを書けるようになる
- 書くことに集中し、量産した結果、自ずと多くの人に読んでもらえるようになる
という流れです。ブログやnoteで記事を書くのなら、この形を目指したい。
ただ、ここでひとつ誤解してほしくないのは、量産フェーズが「根性」や「努力」で作られるわけではないということです。
根性で続けると、どこかで必ず折れます。外からの反応を燃料にすると、反応が落ちた瞬間に燃え尽きます。だからこそ、量産フェーズは「気合い」ではなく、自分の人生観が整った結果として自動的に始まる状態なんです。
つまり、量産とは「自然にそうなる」ものであって、「がんばって目指すもの」じゃない。むしろ、無理に量産を目指そうとすると逆効果で、書くこと自体が嫌になってしまいそうです。
大事なのは量ではなく、量産せずにいられない状態に自分を持っていくこと。そのためには、人生観という土台が欠かせないのです。
僕がブログやnoteでいろんな記事を読んでいて感じるのは、文章のうまさと読まれるかどうかは、あまり相関していないということ。むしろ相関があるのは、「その人の人生観の安定度」だと思います。
人生観が整っている人の文章には、無駄な揺れがない。言葉の選び方がシンプルで、言い切りが迷いない。何より、読んだ後に「この人は、今ここに立って生きている」と伝わる。これはテクニックでは出せない要素です。そして、この静かな説得力にこそ、読者が自然と集まってくる理由なんだろうな、と思います。
一方で、人生観が揺れていると、語尾のニュアンスがぶれる。言葉の温度感が安定しない。文章の軸が読者に伝わらない。すると、不思議なことに、どれだけうまく書いても読まれない。
文章って、本当に正直なんですよ。どうしても「タイトルの付け方」「構成のテンプレ」「読まれるテーマの傾向」とか、テクニックに目が行きがちだけど、そうじゃない。もちろん、これらを学ぶことは悪くないし、僕も必要な場面では戦略的に使っていますよ。
でも、もっと根本のところで言えば、
人生観が整えば、文章なんていくらでも書けるから、テクニックは勝手に身につく。人生観が揺れているうちは、どれだけテクニックを覚えても、その文章は響かない。
これはもう、書き続けている人ほど分かるはずです。
全ては循環している
まとめると、
- 書くことは人生観に支えられている。
- 量を書くにはモチベーションが必要で、モチベーションは「正しいと信じていること」をやると自然に湧く。
- そうやって量産すれば、ようやく読まれるようになる。
- 読まれれば、さらに人生観が磨かれていく。
すべてが循環しているんです。だから順番を間違えてはいけない。「読まれるために書く」ではなく、「自分の人生に沿って書く」→「その結果、読まれるようになる」。これがセオリーだと思います。
だからこそ発信とは、人生観を外側に投影する行為であり、それを続けることで人生観そのものが鍛えられる。だから、読まれる・読まれないは副産物でしかない。書くことそのものが、すでに人生の訓練になっている。
だから僕は、これからも書き続けます。小さな一歩を積み重ねることでしか、未来は開けないのです。