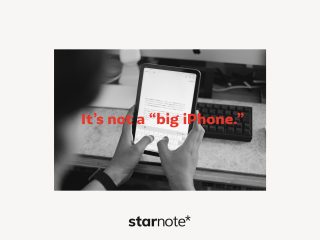漠然と使うのではなく。
この記事には広告が含まれています。
数年前に買ったiPad mini 6。
サイズ感もいいし、持ち運びもラク。なのに、気がつけばずっと机の隅に置かれたまま。「iPhoneが大きくなっただけ」と感じてしまって、つい触る理由を見失っていたんです。
でもあるとき、ふと思いました。iPad miniで「何ができるか」を考えてばかりだったなと。そうじゃなくて、「何を任せるか」を決めないと、僕はこのデバイスを活かせないのかもしれない。
そして試しに、「考える」という役割を与えてみました。寝る前に、自分の思考をゆっくり書き出す。Macを立ち上げるほどでもないけど、iPhoneだと狭い。ちょうどその中間を、iPad miniが気持ちよく埋めてくれたんです。
新しい風が欲しい
1年くらい前から、格安のWindowsノートやChromebookの情報をなんとなく眺めていました。
明確な目的はないんだけど、ちょっと触ってみたいと思ったんです。いつも使っているMacやiPadに不満があるわけでは決してなくて、別の世界も覗いてみたくなるタイミングがあるんですよ。
性能にこだわっていたわけでも、使いたい機能があったわけでもなくて。単純に、触るだけで楽しいデバイスが欲しくなっていたんだと思います。
- 軽い気持ちでいじれるもの
- 目的がなくても遊べるもの
- 少しの刺激を日常に加えてくれるもの
日々の生活が実用一辺倒になっていると、こういう無目的な遊びに惹かれてしまうのかもしれません。
考えていたのは、HPの4万円台のWindowsラップトップとか、ASUSのChromebookとか。きっと日常使用することはないんだろうなと思いつつ、それはそれで楽しい経験になるかなと。
思い出したのは、あの頃のタブレット
そういえば、以前も同じようなことを考えて買ったことがあるなと、ふと思い出しました。
かなり昔の話になるけれど(12〜13年前かな)、8インチくらいのWindowsタブレットが流行ったことがあったんですよ。そのときに買ったのが、Lenovoの「Miix 2 8」というWindowsタブレットでした。
まだWindows 8の時代、小さい筐体なのにフルのWindowsが動くという点に惹かれて、購入したのを覚えています。
- Officeも使えるし、軽い作業もこなせる
- 小さいけれど、いろいろ試せる自由さがあった
- 大学の研究で使っていたソフトがWindows限定だった
今思えば性能は全然よくなかった。でも、何でもできるかもしれないと思わせてくれる自由さと、それでいてコンパクトに収まるサイズ感が、当時の自分にはとても新鮮で、ワクワクしていたのです。
結局数年使って売り払ってしまったのですが、今思い返してもいい経験だったなと。
今はもう違う時代
でも、今はもう違う時代になってしまいました。Apple製品の快適性が当時よりもっと上がっているんです。だからもう逃れられなくなってしまった。
いやね、当時から完成度は高かったけれど、そこにさらなる安定性や機能性が付加されて、これ以上ないくらいの完成度に上がってきています。MacだけでなくiPadの進化も著しい。ただの大きなiPhoneだったiPadが、ここまで生産的なデバイスになるとは思っていませんでした。
さらに、OS間の連携も素晴らしい。macOS・iPadOS・iOSを行き来する際のシームレスな体験が、他のOSとは比べ物にならないくらい快適になりました。
だからこそ、今さらChromebookやWindowsタブレットを買っても、実用的な面では物足りなさを感じてしまいます。「試してみたい」という気持ちはあるけれど、それはもうノスタルジーやロマンの範囲なのかもしれません。
結局、何を探していたのだろうか?
欲しかったのは「使える道具」じゃなくて、「気分を変えてくれる環境」だったのかもしれない。
そう考えると、本当に必要だったのは新しいガジェットではなく、今ある道具の中に「試したくなる余白」を見出すことだったのでは?──という問いに辿り着きました。
そして、その問いを引き連れたまま、ふとデスクの横を見ると、そこにはiPad miniがあることに気がついたんです。
すでに持っていた「ちょうどいい」存在
これ正直に言えば、これまでは「iPhoneが大きくなっただけ」という感覚で使っていました。ブログを読んだり、SNSを眺めたり、Kindleで本を読んだり。iPad miniには、そこまでの役割しか与えていなかったんです。
でも今思えば、それって「何ができるか?」という機能視点でしか見ていなかったんですよね。大切なのはそこじゃなかった。重要なのはこのデバイスに何を託すか?という視点なんだと、ようやく気づいたんです。
だって、Apple製のタッチパネルを搭載したデバイスという共通点があり、iOSやiPadOSという同じようなOSが走っている。だから、機能視点で見ると同じような用途になりがちなのは自明の理です。
「自分がこれらのデバイスにどうやって向き合うか?」をしっかりと定義しないと、同じような使い道になってしまう。僕はそのような定義をしていなかったがゆえに、閉塞感を抱いていたのです。
「考えるための道具」としてのiPad mini
たとえば最近は、iPad miniを縦向きに持って、ソフトウェアキーボードで文章を書くことがあります。その目的は、ブログやnoteの記事を書くというよりも、自分の頭の中にある言葉を丁寧に掬って書き出す。寝る前にベッドに腰掛けて思考を整理するためのデバイスとして、ちょうどいいのですよ。
縦向きでソフトウェアキーボードを使うの、最初は正直、やりづらそうだなと思っていました。でも、実際に使ってみると、その印象は一変しました。
- 両手の手のひらでしっかりと筐体をホールドして
- 親指を真上からストンと下ろすようにして打つ
このスタイルであれば、比較的安定してタイピングできるんです。
さらに言えば、文章の一覧性が高まるというのも見逃せません。iPhoneでは得られなかった、全体が見えるという感覚。この視野の広さが、文章全体の構造を考えるときにとても役に立ちます。
思考の流れを支えるための使い方
僕はこのiPad miniで、よくこんなことをしています。
- Ulyssesで頭の中の思考を書き殴る
- ある程度まとまったら、それをChatGPTに投げて壁打ちする
- 出てきたアウトプットをMarkdownで整理して、Obsidianで保存する
この一連の流れは、Macでもできる。でも、寝る前のちょっとウトウトしたタイミングでこれをやると、いい意味で突拍子もないアイデアが浮かんできたりして、とてもいいんですよ。
ベッドの中にMacを持ち込む気にもならないし、だからと言ってiPhoneだと画面が小さくて一覧性がよくない。だから、iPad miniがちょうどいい。
つまり、どっしり構えて頭をフル回転させてアウトプットするならMac。でも、まだ形になっていないモヤモヤを相手にするときには、iPad miniくらいの距離感が心地いい。本音や直感にアクセスしやすくなる感覚とでも言えばいいでしょうか。
こうやってiPad miniに役割を与えることで、「なんとなく触る端末」から「思考を支える相棒」へと変わっていきました。
意味は自分が与えるもの
思い返せば、Miix 2 8に感じていたワクワクも、性能の問題ではありませんでした。大きな機能はなくても、自分の思考や好奇心が自由に泳げるスペースがそこにあったから楽しかったんだと思います。
iPad miniも、まさにそのポジションにあるはずです。何ができるかではなく、何を託すか。それを考えるだけで、この小さなデバイスは何倍も可能性を広げてくれます。
iPad miniは、機能で言えば中途半端かもしれません。iPhoneより大きくて、iPad ProやMacより非力。でも、だからこそ「ちょうどよさ」がある。
- 思考の補助線になる
- 書く習慣の呼び水になる
- 整理されていない感情に形を与えてくれる
使い方ではなく「託し方」を考える。それが、iPad miniを救うたったひとつの方法だったのです。こうしてiPad miniに「役割」を与えたら、手放せなくなりました。