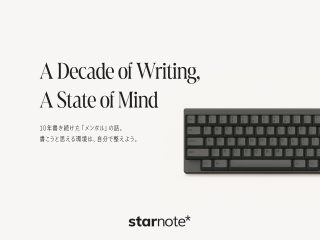こんなの無料で公開しちゃっていいのか?
この記事には広告が含まれています。
先日、個人ブログの時代は終わりじゃない(かもしれない)という記事を書きました。
その中では、2024年8月のGoogleコアアップデートの概要に触れつつ、Googleサーチコンソールの画面を見せながら、個人ブログであってもGoogleと仲良くしていける!という話をしました。
この記事を書いてから3か月ほどが経ちましたが、やっぱりそうだなと。この記事を裏付けるような事象が、ちょうど現在進行形で起きています。それがこちら。

そうです、GoogleアプリやChromeのトップに出てくる「おすすめ記事」。これ、正式名称はGoogle Discoverというのですが、Google検索に含まれる機能のひとつで、ユーザーと相性がよさそうな高品質な記事をGoogleアルゴリズムに基づいて提案しれくれます。
2〜3年前は、記事を公開した直後のタイミングだけピックアップされていたのですが、最近は数日遅れて、かつ長期間にわたってサジェストされ続けるような挙動を示しています。現在進行形で起きている事象の場合、
- 3月29日に記事投稿
- 直後は特に大きな動きはなし
- 4月2日(本日)の朝になってアクセスが急増した
という状況。特にSNSでのバズを起こしたわけでもなく、拡散された様子もないのに、大きく数字が上がるような現象に遭遇した場合、このGoogle Discoverであることが多いです。
アルゴリズムの詳細については僕も専門外ですが、今回の件は「何かが変わった」ことを、改めて裏付ける事象だと感じています。それはGoogleの変化であり、同時に、個人ブログにとって新しいチャンスでもあるのです。
この記事では、その変化の背景を掘り下げつつ、これから個人ブログがどのように向き合っていけばいいのかを考えてみます。
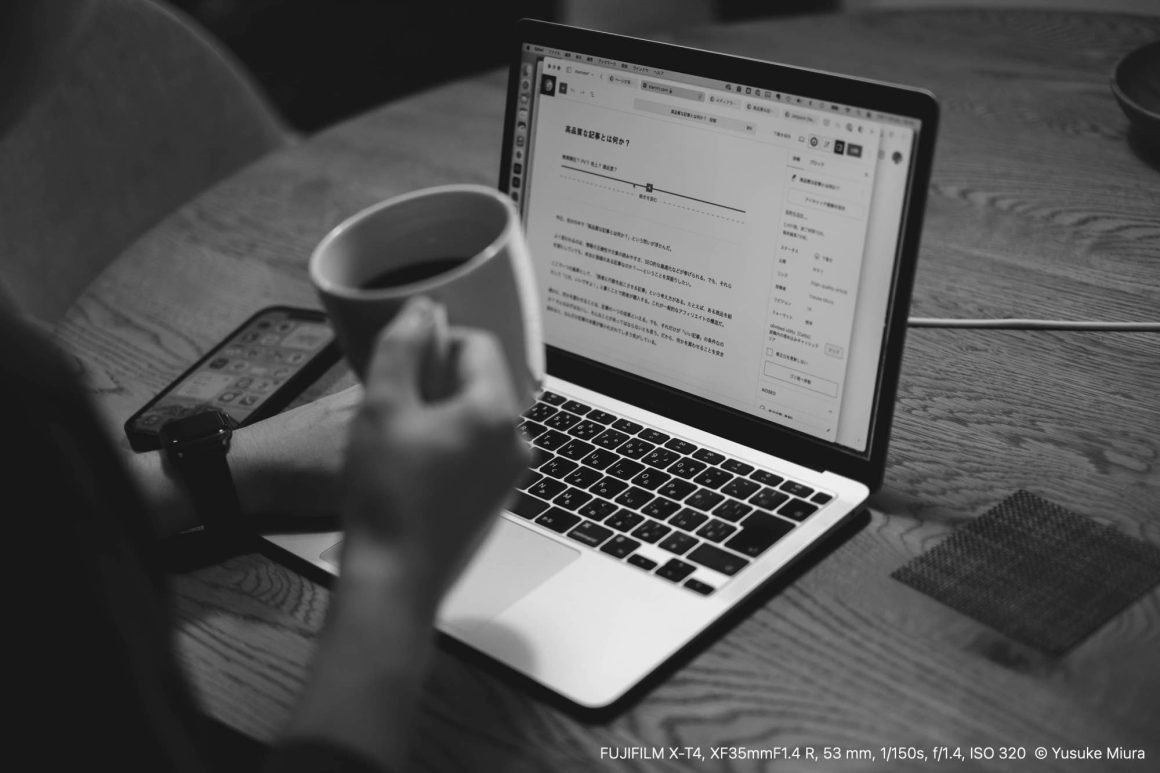
変化したのは「情報」よりも「視点」の価値
ちょっとだけ時系列順に物事を整理させてください。ターニングポイントは、2023年10月と、2024年8月。
まず、2023年10月以前は、たとえ個人が運営するブログであっても、一次情報や丁寧な体験記がしっかり評価されて検索結果の上位の方に掲載されていました。僕自身も、きちんとSEOを考えて上位表示させてアフィリエイトで稼ぐようなことをやっていた時期がありました。
そして1回目のターニングポイントである、2023年10月。これ以降、Googleのアルゴリズムが大きく変化しました。
すなわち、企業や公的機関のような信頼できるドメインが優遇されるようになり、個人ブログが上位に表示されにくくなったのです。おかげでブログ界隈は阿鼻叫喚の嵐で、このタイミングで更新をやめる個人ブログも多くあったように思います。
僕はそんなの知るかと思って更新し続けていましたが、減り続けるアクセスに心が折れそうになっていた2024年8月、2回目のターニングポイントが訪れました。それは、Google公式の記事も出ているけれど、有用な独自コンテンツを作成している小規模サイトにしっかりと光を当てる方針に変化したのです。
その結果、通常のGoogle検索のトラフィックが戻っただけでなく、Google Discoverによる流入も大きく増加しました。検索だけでなく、検索以前のレコメンド型の流入も大きくなってきた。これは個人ブログとしては無視できません。
Googleの言葉を借りると、「有用な独自コンテンツ」ですよ。つまり、単なる情報ではなく、体験を通じた言葉に価値が移ってきていると思うのです。どんな視点で見て、どう感じて、それをどんな文脈で伝えているのか。そうした経験に基づく「語りのスタイル」や「高い解像度」が求められているのだと思います。
個人ブログが評価されるために必要なもの
ただ書くだけでは読まれない。けれど、誰かが読むとき「この人の言葉なら信じられる」と感じてもらえたら、もう一歩先に進める──そんな手応えを最近感じています。
僕のブログも、内容そのものというよりは、語り口や空気感で読まれている実感があります。写真の雰囲気や構成の緩急、そしてひとつひとつの言葉選び。そうした細部が積み重なって、「このブログが好き」と感じてもらえるのではないかと。自分で言ってるだけだったら恥ずかしいけど。
つまり、「何が書かれているか」ということ以上に、「誰が」「どんな視点で」書いているかが問われているのです。書き手の輪郭が自然ににじみ出るような、そんなアウトプットが、これからの時代には必要なのだと思います。
なぜなら、一般的なことはChatGPTにでも言えるからです。このような生成AIでカバーできないのは、個人の体験に基づく感想や意見、その源である視点。だから今後は、「自分がどう感じたか」にしっかりとフォーカスを当て、丁寧に抽出しながら言語化することが、より求められるようになると思います。

SEOからDiscoverへ──検索される前に届ける
これまでブログ運営においては、SEOを意識するのが常識でした。検索されるキーワードを考え、記事タイトルを調整し、網羅性のある内容を意識する。僕自身もそうした時代を長く経験してきました。
しかし今、Google DiscoverやGoogleニュースのようなレコメンド型の導線が力を持ち始めています。検索される前に記事を発見してもらえる仕組みが、改めて整いつつあるのです。
この記事の冒頭でも書いたけれども、実際にこのブログでも、Google Discoverに掲載された記事が突如として高いPVを記録し、その後もしばらく流入が継続するという現象が何度も起きています。それが今回も再現性を持って裏付けられたと。
このようなレコメンド型の流入を得るためには、従来のSEO対策とは異なるポイントが必要です。
- タイトルがシンプルで直感的に伝わること
- サムネイルが視覚的に魅力的であること
- 内容が「体験ベース」で読みやすいこと
これって、YouTubeで「大切なお知らせ」のようなシンプルなタイトルの動画が見られやすいのと同じ構造でして。つまり、検索ワードを意識した記事構成よりも、「誰かのタイムラインに現れたとき、思わずクリックしてしまうか?」という観点で考えた方がいいということ。
そして、Google Discoverに掲載される記事にはいくつか共通する特徴があると言われています。
- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性):特に “Experience(経験)” に基づいた体験記事が評価されやすい傾向にあり、これは当ブログと非常に相性がいい要素だと思われます。
- コンテンツの質:誤字脱字が少なく、一次情報に基づいており、主観と客観のバランスが取れていること。
- ユーザー関心との一致:検索履歴や閲覧履歴に沿った話題であればあるほど、表示される確率が高くなる仕組み。
- 視認性や表示の最適化:高品質なサムネイル画像や、記事内の画像サイズ、読みやすいレイアウト、速い表示速度なども影響すると言われています。
SEOは「検索される記事」を目指すものでしたが、Google Discoverでは「見つけられる記事」であることが重要になります。この違いを理解することで、アウトプットの戦略も自然と変わってくるはずです。
「情報量」では勝てない時代に、書けることを書こう
情報をたくさん持っている人が強い──そう思われがちな時代が長く続きました。しかし最近では、「自分にしか書けないこと」を持っている人のほうが、より深く読まれていると感じます。
誰かの体験をなぞるだけではなく、自分自身の体験を通して感じたことを、自分の言葉で語る。それができる人の文章には、自然と熱量や説得力が宿ります。
AIの台頭によって、一般的な情報はどこでも手に入るようになりました。だからこそ、「個人が何を感じ、どう解釈したか」という視点の希少性が、より際立ってきているのです。たとえば、日常の中で感じたちょっとした不便や、仕事で悩んだある瞬間の心の揺れ。それらは検索されないけれど、誰かの心に深く刺さる可能性を秘めています。
これからは、書く範囲を絞り込むことが、むしろ強みになるのかもしれません。広く浅く書いて読者に “So what?” が残る記事ではなく、狭く深く書いて読者に熱量を伝え納得感を持ってもらう。そんな時代が来ているように思います。

個人ブロガーが今やるべき5つのこと
ここまで紹介してきた変化を踏まえて、個人ブロガーとして今できることを5つに整理してみました。
Google Discoverを意識した「表現力」のアップデート
Google Discoverでは、タイトルやサムネイル画像、そして本文冒頭の文体がとても重要です。意識すべきは「どこかで見たことある情報」ではなく、「思わず開いてしまうような言葉」です。
文章力というより、「見せ方」の更新と言っても良いかもしれません。このあたりで僕がどのようなテクニックを使っているか?というような話は、今度有料noteで出そうと思っています。
見た目を整える(サムネイル、タイトル、リード文)
視覚的な第一印象は、思っている以上に重要です。タイトルとサムネイルの組み合わせで、「この人の記事を読んでみたい」と思ってもらえるかが決まります。リード文もまた、読み手の興味を引く「フック」になります。冒頭の数行にこそ時間をかけたいところです。
僕の場合は、記事を書き始めたときに仮で適当に書いておいて、最後まで書き終えてから冒頭に戻ってきます。そのうえで、記事全体とのバランスを見ながら、タイトルと冒頭の流れを調整しています。バランスを考えた結果、手を加えないこともありますが。
書きたいこと×読まれたい欲のバランスを見直す
書きたいことを優先しすぎると独りよがりになり、読まれたい欲を優先しすぎると空虚になります。大事なのは、そのバランスを取りながら、自分の熱量と読み手の関心が交差するポイントを見つけることです。
こればっかりは経験しかないと思いつつ、根幹は仕事上のコミュニケーションと同じだと思っていて。会議の中で無駄な要素を排して、過不足なく要点を伝える。誤解が生じやすい部分は繰り返し言い換えながら温度感を伝える。そういうことです。
過去記事の見直し・再構築
2024年8月以降のGoogle Discoverは、意外と「少し前の記事」も拾ってくれます。だからこそ、過去に書いた記事のタイトルやリード文、サムネイルをリフレッシュするだけでも再評価される可能性があります。
僕も大きなリライトはほとんどやらないですが、過去の記事を読んでいるときに誤字脱字に気づいたら、その場でサクッと直しちゃいます。このようなリライトや微調整も、立派な「新しい発信」です。
「何を書く人か」を決める
最近よく思うのは、「この人は何について書く人か」が伝わるだけで、ブログの印象が格段に強くなるということです。幅広いテーマを扱っていても、「芯となる興味関心」が明確であれば、読者は安心して回遊してくれます。
それは決してひとつのテーマに絞ることではなく、タグラインやプロフィール、記事のトーンなど、いろんなところに「自分らしさ」を軸としてにじませていく。当ブログで言うと、文体、サムネイル、文章のリズム。このあたりかな。
最後に:人間らしさを取り戻す時代へ
アルゴリズム、SEO、AIと、テクノロジーが進化するたびに、ブログという営みは少しずつ変化してきました。けれども、どんな時代でも変わらないものがあるとすれば、それは「人間の言葉に惹かれる」という感情だと思います。
誰かの目線で見た風景、誰かの言葉で綴られた体験、それを通して自分の中に新しい視点が芽生える。ブログには、そんな体験を届ける力があると信じています。
情報ではなく、視点がある。
体験ではなく、物語がある。
実用性ではなく、余白がある。
このような世界観をブログの中に作り出すことができれば、「この人の言葉をもっと読みたい」と思ってもらえるはずなのです。そのような世界観を作り出すための文章力は必須だけれども、そんなの書いて書いて書きまくればいずれ獲得できる。その成長の過程においても、ちゃんと自分の世界観を考えたいね、という話。
だからこそ、僕はこれからも、自分のペースで、自分の言葉で、書けることを書いていこうと思います。そしてこの変化の時代を、むしろ楽しみながら進んでいきたいですね。