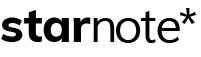いつの間にか冬だった。
この記事には広告が含まれています。
妻と一緒に、近所のスーパーへ行った。翌日のおでんの材料を買いにいく、というだけの理由だ。大根やこんにゃく、練り物を思い浮かべながら売り場を回る。
店内は明るく、空調が効いていて、冬の輪郭はきれいに均されている。鍋に入れるものを選び、会計を済ませ、袋に入れる。その一連の流れに、季節が割り込む隙はほとんどない。
自動ドアが開いて外に出た瞬間、息を吐いたら白かった。思わず声に出してしまった。こんなに寒かったっけ、と。
妻は少し間を置いて、もう二月だけど、と言った。それはそうだ、と頷きながら、なぜか可笑しくなった。暦が間違っているわけではなく、自分の感覚が少し遅れていただけだと分かったからだ。
最近は、夜に外へ出ることが少ない。
出社しても用事が済めば早めに切り上げて、まだ明るいうちに帰る。在宅で済む日は、家から出ないまま一日が終わる。寒さは、エアコンの設定温度と天気予報の数字で処理される。冬はそこにあるけれど、触れなくても生活は成立する。
スーパーの中にいる間、冬は完全に脇に置かれていた。明るさも、匂いも、音も、すべてが均されている。おでんの材料を抱えて外に出て、息が白くなって、はじめて思い出した。ああ、今は冬だったんだ、と。
白い息は、何かを主張するわけでもなく、ただそこに現れて、すぐに消えた。その短さが、かえって印象に残った。
在宅中心の生活は快適だ。無駄がなくて、静かで、コントロールしやすい。その代わり、触れなくていいものは、自然と触れなくなる。夜の冷気や、吐いた息が白くなる瞬間みたいなものは、こちらから外に出ない限り、向こうからはやってこない。
息が白いことに驚いた、というのは、季節に置いていかれていたという話ではない。自分の生活が、どんな感覚を後回しにしているかに、ふと気づいたというだけのことだ。
妻と並んで歩きながら、買い物袋の重さを感じていた。さっき見た白い息のことを、わざわざ口に出すことはなかった。ただ、おでんの鍋の湯気と、店の外に広がっていた冷たい空気が、同じ季節の中にあることを、静かに思い出していた。