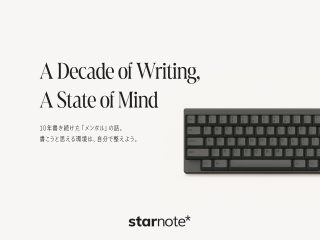元審査専門員がお答えします。
この記事には広告が含まれています。
PMDAの就活、傾向と対策
僕は薬学系の博士課程を修了した後、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に入社し、2年4か月ほど新薬審査を中心に携わっていました。
もちろん、通常のルートでPMDAに採用されました。PMDAのWebサイトの採用情報のページやマイナビから情報を収集した上で応募し、書類選考や面接をクリアして内定を貰い、入社式の日に辞令が出て新薬審査部に配属されました。
その中で得られた経験や、採用関係者から聞いた話もあります。この記事では、外に漏らしてはいけないラインに配慮しつつ、僕のPMDAの就活の経験を紹介し、Twitterでよく頂く質問についてまとめています。
おことわり
僕は採用担当でも人事でもなく、ごく一般の審査専門員でした。採用に関することは関係者から耳にしたことはありますが、直接関わっていないことはご理解の上でお読みください。また、情報が古い可能性もあるので、参考程度でお願いします。就活生の皆さんが何も情報がない中で活動するのは不安だと思うので、少しでも役に立てたらと思って筆を取った次第です。
もくじ
選考フローとその内容
現在は分かりませんが、僕が就活していたときは以下のようなフローでした。2019年4月入社なので、就活していたのは2018年3月〜6月。
- 3月20日くらい?:ES提出締切
- 5月6日:テストセンター受験締切
- 5月16日:一次面接
- 6月5日:最終面接
- 6月7日:内々定
マイナビ経由で応募した後、ESのフォーマットをダウンロードし、印刷して郵送しました。なぜ今どきWeb提出じゃなくて郵送?と思った気がしますが、後から聞いた話だと書類選考を紙ベースでやるから、とのこと。
テストセンターは他企業の選考で受験したものを送信しただけだったので、特に工数は発生しませんでした。
一方、面接は東京・霞が関のPMDAオフィスでやるので、わざわざ出向く必要がありました。交通費は出ません。当時は長崎に住んでいたので高い交通費を払わないといけませんでしたが、幸運なことに交通費の出る他企業の選考と日程が近かったので、手出しはゼロで済みました。
以下、当時の記録を元に書き起こしました。ご参考程度にお願いします。
書類選考
指定のフォーマットで、履歴書、自己紹介書、研究内容、業務履歴、その他PMDAの業務に役立つ知識・経験について書きました。
自己紹介書には志望動機を書く欄もありましたが、それらしい理由を作って書きました。また、業務履歴には、大学院生時代に学部生の講義をサポートしていた「ティーチングアシスタント」の経験を、その他の経験には国際学会で発表したことや学会で受賞したことなどを書きました。
一次面接
一次面接の面接官は4人。複数の会場がありますが、普段は製薬企業と事前面談をしているような会議室です。僕の会場は非常に和やかな雰囲気でしたが、その会場のカラーなのか、応募者ごとに態度を変えてるのかは不明です。
ESを深掘りするという、至って普通の面接でした。また、審査報告書を読んできたか聞かれるので、目を通して行った方がいいです。僕は直前にスタバに籠もって繰り返し読んでました。
議論するときに大切にしている視点や、人を丸め込むことが多いかどうかなども聞かれました。「誰が言ったかではなく、何を言ったかが大事だと思うので、出された意見を中立的に判断しています」と答えたような気がします。
面接時間は20分の予定でしたが、15分くらいで終わって少し焦ったのを覚えています。今考えたら、通過させて問題なかったので早く終わったんでしょうけど。
最終面接
最終面接は一次とは別の役員会議室で実施。面接官は理事長を含む7人くらいで、質問するのは4人くらいでした。
時間は10分間。確認程度だと思っていましたが、そんな甘いものではありませんでした。一次面接よりも踏み込んだ質問も飛び交う始末です。ただ、後から聞いた話では、最終面接は学生を威圧しながら人柄を見抜くのが目的のようなので、落ち着いて質問に答えれば大丈夫です。
- 1人目(理事長):サークル活動や性格について。
- 2人目:薬物動態について。解析に関するソフトを使ったことがあるかなど、踏み込んだ質問もありました。
- 3人目:現在行っている研究について、口頭で1分くらいで軽く説明するように求められました。想定外だったので少し焦りました。
- 4人目:ティーチングアシスタントの業務に関すること
偉い方々が質問している間は、理事長は目を瞑って難しい表情をしています。それがちょっと怖かったです。ただ、2019年に理事長が代わっているので、今の最終面接の雰囲気は違う可能性があります。
よくある質問への回答
元PMDAであることをブログやTwitterで明かしていると、就活に関する質問を頂く機会が何度もあります。僕の回答の中から、質問者の個人情報を削除し、記事向けに再構成した上で掲載します。半分以上が書き足した内容です。
博士卒の方が採用されやすい?
まず、よく聞かれるのが「今は6年制や修士課程だけれども博士人材の方が採用されやすいか」という点。結論から言うと、PMDAに採用されることを目的とするのなら、博士でなくても全然大丈夫です。ただ、審査部への配属を希望するのであれば持っていた方が可能性は高くなります。
あまり詳しくは書かない方がいいと思うので、雰囲気で察していただければ幸いです。僕の同期が2ケタ人いますが、6年制卒:修士卒:博士卒の割合はちょうど同じくらいでした。博士があからさまに多いわけでもないので、PMDAに入社すること自体が目的なら博士を持っていなくても問題ありません。
一方、審査系の部署に配属された人に着目すると、結構な割合が博士持ちでした。つまり、新入社員のうち1/3程度の博士持ちの人材が、審査系の部署に局在しているのです。この事実をどう捉えるかは、個々人の目的次第ですね。
とりあえずPMDAに入社すること自体が目的で、安全対策や救済をやりたいんです、ということなら、博士はなくていいと思います。一方、入社直後から審査系の部署に配属され、審査や対面助言に関わっていきながら、薬事のプロになりたいのであれば、博士卒の方がそれができる可能性が上がります。
審査部に配属されたいから博士進学するのはどう?
ここで悩ましいのが、「現在6年制 or 修士課程に在学中だけど、審査に携わりたい」という場合。
上記のような状況なので、審査に関わりたいと強く思っている学生さんほど、「PMDAに就職して審査部に配属されるために博士に行く」という思考になってしまいます。でも個人的には、それは止めたいです。
理由は3つ。
- そもそもPMDAに採用されない可能性があること
- 博士の学位を持っていても、希望する審査部への配属にならない可能性があること
- 博士の学位を持っていなくても、審査部で活躍している人が大勢いること
博士を持っていても持っていなくても、選考で落ちる可能性があります。時間と労力とお金をかけて博士課程に進学したのに、そもそも採用されなかったら意味がありません。リターンよりリスクの方が大きいです。
また、博士の学位を持っていると審査部への配属の可能性が高くなるとはいえ、「医薬品」「医療機器」どちらの審査部への配属となるかは分かりません。学生時代の研究内容を踏まえて配属されることが多いですが、100%ではないのです。
さらに、審査部の中で博士の学位を持っていなくても活躍している人は大勢います。例えば、定年までPMDAで働いて上まで登り詰めたいのであれば、博士はあった方がいいかもしれません。でも、数年働いて転職することを前提とするのなら、博士はなくていいです。
ただ、もちろん、他にもやりたいことがあって、そのためには博士が必要で、通過点としてPMDAの審査部に行きたい、ということなら博士進学も選択肢に入ると思います。
医療機器ではなく、医薬品の審査部に入りたい
これは運の要素も大きいですね。面接のときに医薬品の審査に関わりたいことをアピールした上で、研究内容のバックグラウンドも考慮されます。
と言いながら恐縮ですが、僕の場合は大してアピールしなかったものの、研究内容から判断されたのか、中枢神経系の医薬品を審査する部署に配属されました。
仮に医療機器の審査部に配属された場合でも、数年働いた後で医薬品の審査部に異動になる可能性はあります。年1回、やりたいことに関する面談があるので、その中で希望を出す感じです。知り合いの事例だと、博士(薬学)の取得後にPMDAに入社して医療機器の審査部に配属され、2年後に医薬品の審査部に異動した事例があります。
PMDAの中では、2〜3年スパンで異動させながらいろんな仕事を経験させる方針なので、最初の配属が医薬品でなくても悲観することはないと思います。
ただ、僕のように「2〜3年でPMDAを辞めて〈元PMDA〉の肩書きを使って転職しよう」と考えているのなら、話は別です。最初の配属が重要なので、面接の中でしっかりアピールした方がいいと思われます。
面接の対策、どうすれば?
今はどうか分かりませんが、僕のときは書類選考とテストセンターの後、一次面接と最終面接がありました。一次ではPMDAで仕事をする能力があるかどうかが見られ、最終では人間性(この人と一緒に働きたいか)が見られると聞きました。
なので、個人的には何か準備が必要なわけではなく、聞かれたことに素直に答えればそれでいいと思います。実際、僕も1品目を選んで審査報告書を読んでいった程度で、あとは聞かれたことに素直に受け答えしただけです。なので、対策らしい対策はしてないです。
面接ではどのような部分を見られますか?
正直なところ、面接官ではないので分かりません。しかし個人的には、質問に対して誠実に回答し、言葉のキャッチボールができていればいいと思います。
回答の内容が評価されたのか、ちゃんと回答したこと自体が評価されたのか、それとも別の場所に評価ポイントがあるのか、よく分かりません。ただ、後から考えると、PMDAでは皆の考えを寄せ集めながら議論することが多いので、回答の内容や姿勢が評価されたのかもしれません。
審査報告書を読んでみた感想、聞かれますか?
読んでみた?どうだった?書けそう?と聞かれた気がします。それくらいフランクな会でした。
審査専門員側は一言一句まで相当こだわりを持って審査報告書を書いてるので、ただ単に学生の感想を聞きたいだけなんじゃないかと思っています。読んできたこと自体は評価されるかもしれませんが、答えた感想次第で採用・不採用が変わるとは思えません。
医薬品の審査部ではどんな仕事をしてますか?
医薬品の審査部は、新薬審査第一部〜第五部、再生医療製品等審査部、ワクチン等審査部、ジェネリック医薬品等審査部などの各部署に分かれています。
その各部署において、臨床、統計、毒性、薬物動態、品質、薬理の各分野担当がいて、皆がそれぞれの観点から品目を見ています。各分野担当ごとに違う仕事をしているわけではなくて、違う視点から同じ仕事をしています。
仕事内容は以前記事にしたとおりで、審査の他にも対面助言(治験相談)、事前面談、治験届調査などをやってます。詳しくは以下を。
→ PMDAの新薬審査部ってどんな仕事してるの? 元審査専門員が紹介します。
ちょっと分かりにくいので対面助言の例を挙げると、治験成分記号ABC001の医薬品第Ⅱ相試験終了後相談に対して、部長、審査役、主担当1名、副担当1名、臨床担当2名、統計担当1名、毒性担当2名、動態担当1名というような構成でアサインされて対応していきます。
部長と審査役以外は各々の担当分野があるので、例えばABC001の対面助言には動態担当としてアサインされてるけれど、別のXYZ999の対面助言では主担当をやってる、みたいな状況が生まれます。というように、誰もが複数の案件に同時進行で関わりながら、仕事を捌いています。
大学生・大学院生がPMDAで活かせるスキル、ありますか?
6年制や薬学部や修士課程に通っている人が最低限の科学的・論理的思考力があることを前提とすると、あえて言うなら「文章力」だと思います。卒論・修論をはじめとして、国立薬学部の修士なら査読付き論文を書くことも珍しくありません。その中で培った文章力は重要です。
PMDAの審査部では、科学や薬学の知識をもとに資料を読み込んで議論するのはもちろんですが、メディカルライターとしての側面もあるんです。審査も対面助言も、自分やチームの考えをひたすら文章に落とし込んでいく作業なので、個人的には、大学・大学院の研究の中で獲得しPMDAで活かせたスキルは「文章力」だと思います。
まとめ
以上、PMDAの就活の流れとよくある質問についてお届けしました。この内容で多くの方々の疑問が解決できていたらいいのですが、なかなかそういうわけにもいかないと思います。
もし質問があれば、可能な範囲で全然答えるので、TwitterでDMやリプライを飛ばしていただければ幸いです。
Follow @info_starnote