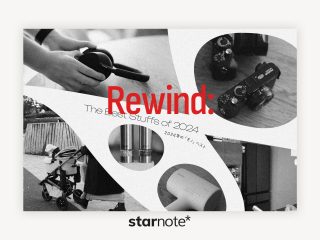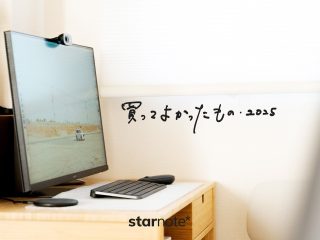もっと自由でいい。
この記事には広告が含まれています。
「道具」って、いい言葉だと思う。
それがないと困るけれど、あるからといって崇拝するものじゃない。ちょうどいい距離感で、日々を少しだけ快適にしてくれる存在。それを使うことで人生が変わる可能性は少ないかもしれないけれど、小さなストレスは軽減される。
そして、道具の価値は、機能が提供されることにある。
ひとつだけの機能を提供する道具もあれば、いろいろな機能を兼ね備えている道具もある。我々は、その道具を使って物事を処理して、また次の物事に取り掛かる。機能が提供されればいいから、使っている人間にはそれ以上の感情が乗らない。
僕にとって、ガジェットも、そういう存在であってほしいのです。
たとえば、iPhone。
僕も長年使っていて、日々の生活に欠かせない存在になっています。写真を撮る、メモを取る、LINEを送る、CarPlayで車に接続してナビにする──まさに万能な道具です。かつては専用の道具が必要だったものが、今やiPhoneだけで済んでしまう。
でも、僕の場合は「愛機」とか「相棒」とか、そういう言葉で語る対象ではない。あくまでも、必要だからそこにある。短いスパンで買い替えることにも抵抗はないし、毎日肌身離さず持ち歩いているにもかかわらず、そんなに愛着はないんです。
Macも同じ。
M1 MacBook Airを使い始めてからもう何年も経つけれど、いまだに不満はありません。軽くて、静かで、電池が長持ちする。それだけで十分だと思っています。
日常的に、文章を書いたり、写真を現像したり、ブラウザで調べものをしたり。そういった作業がストレスなくできるなら、それでいい。たとえ3倍速くなったとしても、それを体感するシーンが僕の暮らしにはほとんどない。
もちろん、新しいものが出るたびに性能をチェックしているし、興味がないわけではありません。でも、その興味はどこか冷静で、どこか引いたところにある。たとえるなら、遠くの島で開催されているお祭りを、海岸から眺めているような感じ。
そして、そんな「お祭りの熱気」を最も象徴的に感じるのが、充電器というジャンルだと思っていて。
充電器は、まさに「ただの道具」の最たるものだと思います。デバイスに電力を供給する、ただそれだけの役割を担っている。それ自体が何かを生み出すわけではないし、そこに創造性があるわけでもない。裏方の存在です。
それでも、新型の充電器が発売されると、界隈は静かにざわつく。
「出力がアップした」とか、「プラグが折りたためるようになった」とか、「世界最小サイズを更新した」とか、そういった微細な変化に反応する人たちがいるじゃないですか。誰とは言いません、この文章を書きながら誰も思いついていないので本当です。
僕はそんな光景を目にするたびに、充電器メーカーの企業努力に感心する一方で、心が揺さぶられることはありません。
これは、「その熱量がおかしい」と言いたいわけじゃないのです。むしろ、そこに本気で興奮できる感性を、ちょっと羨ましいとも思っているくらい。でも、僕はその感覚を持ち合わせていません。そんな温度感。
一部の音楽マニアがケーブルの材質にこだわるように(もっと言うと電力会社によって音質が変わるというオカルトすらあるように)、調理器具マニアが火加減の伝わり方に敏感になるように、ガジェット好きは「電力をどう届けるか」に夢中になれる。
それはひとつの感性だし、美学だと思います。ただ僕は、そこにはどうしても乗り切れないんですよ。
充電器に対しては、機能さえ果たしてくれればいいという気持ちがあります。壊れにくくて、サイズがそこそこ小さくて、重すぎなければOK。むしろ付属の充電器をそのまま使っても何も問題ありません。
いま使っているAnkerのUSB-C PD充電器は、数年前に買ったもので、MacBookもiPadもiPhoneも、すべて問題なく充電できています。これ以上の性能は必要なく、壊れるまで買い替える意義を感じません。
そう考えると、「熱狂しない」というのも、ある種の立場なのかもしれないな。
興味がない人は、そもそもガジェットの話題にすら関心を持たない。けれど僕は、ガジェットが好きだ。ニュースもチェックするし、新製品のレビューも見る。スペックシートにも目を通すし、技術の進化には素直に感心する。
でも、「それを持つこと」自体に喜びを感じるというより、「それをどう使うか」にしか関心が向かない。ガジェット好きの中では、少し異質で冷ややかな態度なのかもしれません。普通の人からしたら普通のことだと思うけれども。
でも、だからといって、自分のことを「意識高い逆張り系」だとは思っていません。
むしろ、僕は怠惰なんです。興味があるものだけを最大限の熱量を持って選び、興味のないところはスルーする。ガジェットに限らず、情報も流行もそんなふうに取捨選択しているから、いつのまにか熱狂の波に取り残されてしまう。
充電器に限らず、最新のMac、最新のiPad、最新のiPhoneからも取り残されてしまいました。そして、取り残されたまま数年経って、ふと気づいたんですよ。「あれ、意外と快適だな」って。
最近だと、すごい!と思った人たちがレビューしてくれるから、必要な情報だけ拾えばいい。欲しい!と思った人たちが買って試してくれるから、僕はそれを見て満足できる。
言い方は悪いけれど、最前線で盛り上がってくれている人たちがいるおかげで、僕みたいな冷めた観客にも、ちゃんと居場所があるんだと思います。
とはいえ、僕がこういう態度をとるようになったのは、最初からではありません。
昔はもっと熱量がありました。Appleイベントがある日は深夜に起きて、リアルタイムで発表を追って、その後の記事を読み漁っていました。毎年のiPhoneの進化がとても楽しみだったし、Apple PencilがiPad Proにマグネットでくっついたときは、興奮で夜しか眠れなかったね。
でも、そういう体験を重ねる中で、自分にとっての「ちょうどいい熱量」の範囲が見えてきたんです。「これはいいな」と思う。でも「今すぐ必要ではない」。その間にある静かな感情を大事にしたいという、もっと自然なスタンスになってきました。
感情の熱量がゼロになったわけじゃない。けれども、ガジェットへの熱量を維持できるほど、「余白」がない。ガジェットのことばかりを考える暇もないし、ライフステージが進むにつれて、家や車などの他の高額商品にも目を向けるようになりました。
だから、心の温度は少し低めのままでちょうどいい。そんな日々です。
こういうスタンスでガジェットに接していると、面白いことがあります。
新しいものが出ても、「買わなきゃ」というプレッシャーを感じないんです。比較レビューを読んでも、「うん、今使っているモデルでも十分かな」と納得できる。むしろ、「まだまだこれで戦えるな」と確信するたびに、ちょっとした安心感が生まれる。
買わないことを選択できるし、その自由が何よりも嬉しい。このような自由を手に入れるために必要なのは、「道具として見る」という視点なんだと思います。
「ガジェットが好きで、信仰しない」という立場は、一見すると中途半端かもしれない。でも、どっちつかずなように見えるそのバランスの中に、僕は確かな心地よさを感じています。
日々の作業を、静かに、淡々とこなす。そしてその傍らに、信頼できる道具がある。それが僕にとっての「ガジェット」であり、それ以上でもそれ以下でもありません。
ガジェット好きであることと、信仰しないこと。それを意識して両立させているのは、意外と少数派なのかもしれません。「これでいい」と思えたとき、ガジェットは自由になるのです。