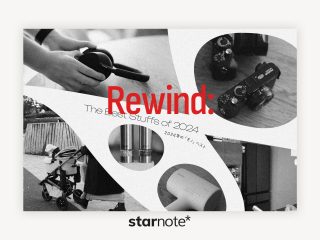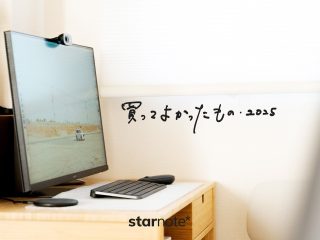試行錯誤の結果を全てお伝えします。
この記事には広告が含まれています。
僕が今乗っているMAZDA CX-60は、そのボディ造形の美しさを最大限に引き出せる「ロジウムホワイトプレミアムメタリック」という色を選びました。光が当たると真っ白に、日陰ではシルバーにすら見える、美しい色です。
これ、要するに「白い車」ということでして、その白さを美しく保つためには、定期的なコーティングと日々のメンテナンスが不可欠です。
このようなメンテナンスには人それぞれ考えがあると思いますが、僕がやっているメンテナンスを細分化すると、
- 塗装面を守るガラスコーティング(1〜1.5年に1回)
- 水垢を落とす洗車(3〜4か月に1回)
- 日常的な洗車(3〜4週間に1回)
このような感じになります。
まもなく納車から2年半。納車直後からこのようなメンテナンスを心がけていると、今でもまだ新車のように綺麗な輝きを維持できています。だから特に変なことをしていると思えないし、むしろ積極的におすすめしたいメンテナンス方法です。
この記事では、その詳細をお伝えするとともに、いろいろ試した先にたどり着いた洗車道具のご紹介もしようかなと。できるだけ手間をかけずに、でもきれいに保つ方法を模索してきたので、参考にできそうな部分はぜひ取り入れていただけると嬉しいです。
もくじ

塗装面を守るガラスコーティング(1〜1.5年に1回)
せっかく新車を購入したのなら、きれいな状態で長く乗りたい。特に、ロジウムホワイトプレミアムメタリックは「匠塗 -TAKUMINURI-」という有料色なので、汚くなってしまったら台無しです。
そう思って納車日にコーティングを施行しました。ディーラーオプションのコーティングではなく、近所のキーパーラボに持ち込んでクリスタルキーパーを施工。記事執筆時点のメニューは以下なので、いちばん安いメニューです。
| メニュー | 内容 | 耐久年数 | LLサイズ価格 [税込] |
|---|---|---|---|
| EXキーパー | 最高級の美しさと防汚性。ノーメンテでも長期持続。 | ノーメンテ3年 年1回メンテで6年 | 163,400円 |
| Wダイヤモンドキーパー | ダイヤモンドキーパー2層仕様。深いツヤと高耐久。 | ノーメンテ3年 年1回メンテで5年 | 108,000円 |
| エコダイヤキーパー | 環境に配慮した超撥水型。手間が少ない。 | ノーメンテ3年 または2年ごとメンテで5年 | 108,000円 |
| ダイヤモンドキーパー | 高密度ガラス被膜。コスパと美しさのバランス。 | ノーメンテ3年 年1回メンテで5年 | 67,600円 |
| フレッシュキーパー | 雨で汚れが落ちる設計。短時間施工。 | 1〜2年 | 40,300円 |
| クリスタルキーパー | 年に1回手軽にかけ直すコスパ型。 | 1年 | 29,800円 |
このようなコーティングはお守りのようなもので、別に高いコースを選ばなくてもいいと思っています。最低限のクリスタルキーパーでもしっかりとガラス被膜はあるので、僕はこれで十分。
また、クリスタルキーパーは年1回の再施工が必要なのですが、2回目のコーティングは1年半くらい経ってからやりました。それでも感動するほどに艶が増したので、別にしっかり1年を守らなくても全然問題ないと思います。
鉄粉取りも同時施工(特に白い車は)
そして、再施工時には鉄粉取りもお願いしました。
道路上にはブレーキダストなどが由来となった小さな鉄粉が大量に落ちているため、普通に走るだけでその鉄粉が舞い上がってボディ表面に突き刺さります。それを定期的に除去しないと、塗装面に不可逆的なダメージを与える原因になったり、錆びて色が付いたりします。
特に白い車だと、鉄粉が錆びたら茶色いスポットになるので、めっちゃ目立ちます。それだけで一気に見た目がくたびれてしまうので、できるだけ除去したいところ。
また、コーティングを再施工(つまり上塗り)するときに、鉄粉が残ったままだと、コーティング面の中に取り残されてしまいます。こうなったら除去するのは大変なので、できるだけ表面をきれいにしてからコーティングを再施工するのがいいです。

水垢を落とす洗車(3〜4か月に1回)
しかし、このガラスコーティング。普段からしっかりメンテナンスししないと、一瞬で汚くなってしまいます。そして水弾きも悪くなる。
その原因は、表面に付着した水垢だと言われています。付着したままで放置していると、汚れが下層へと浸透していき、塗装面へのダメージが不可避。
もちろん、ダメージがコーティング面だけに留まっていれば、下層にある塗装面へのダメージは回避することができます。とはいえ、わざわざコーティングを全部剥がして再施工しないですか。だからそんな状態にならないように、きれいに保ちたい。
そのために重要なのは、日常的な洗車と定期的な水垢取り、そして上記の鉄粉取りです。
水垢取りは、一般的には「スケール除去剤」というもの使います。これは強力な酸性の溶剤で、表面に付着した水垢を浮かせて剥ぎ取ることができます。でも、キーパーコーティングへの影響が調べてもよくわからないんですよね。
なので、もはや自分でやるのは諦めました。キーパーラボの洗車コースのトッピングメニューに「ミネラル取り洗車」というものがあるんですよ。キーパーコーティング施工車限定メニューで、通常の手洗い洗車に540円 [税込] を追加するだけでやってもらえます。
この価格だったらもうこれでいいじゃんと。変にリスクを負って自分でスケール除去をやるより全然いいです。そもそも自分でやるの面倒くさいし。
日常的な洗車(3〜4週間に1回)
そして、車をきれいに保つことの基礎は、日常的な洗車にかかっていると言っても過言ではありません。
とはいえ、毎回プロのようにしっかり洗車するための時間と労力がないので、普段やるのは最低限です。余裕があれば、そこにいくつかオプションを追加してやっている感じです。
コイン洗車場で手洗い洗車
僕の場合は手洗い洗車が基本で、洗車機に入れることは滅多にありません。洗車機を使うのは本当に時間が取れないときだけで、年に1回あるかどうかくらいの頻度。
自宅マンションで洗うことはできないから、コイン洗車場に行きます。本当にコインを準備するのは面倒すぎるので、キャッシュレス対応の洗車場を選んで行っています。最近、家から割と近くにできたんですよ。
しかし、自宅洗車と違って、コイン洗車場の場合は水を使うタイミングが限られます。こまめに出して止めてを繰り返すのではなく、まとめて流さないといけないので、ちょっとコツが必要です。

実際の手洗い洗車フローと、使っているアイテム
じゃあ僕が実際にどのようなフローで洗車しているのか? ということを、ここからはお伝えします。YouTubeのディテーリング動画をいくつも参考にして、その要素を自分なりにコイン洗車場に最適化しました。
これまでいろんな方法を試してきて、あーでもないこーでもないと取捨選択しながら、「きれいに保つために必要な内容を、自由度の少ないコイン洗車場においても適切に行う」ことを重視したフローです。
基本のフローは以下のとおり。ただ、時間とやる気に余裕があったり、あまりにも汚れがひどい場合は、オプション的に手順を追加するようにしています。
コイン洗車場における手洗い洗車の基本フロー
- 洗車ブースに入庫
- まずはシャンプー液を作ってタイヤを洗う
- [オプション] ボディに泡をかけて汚れを浮かし、その間にディテーリングブラシで細かい部分の汚れを掻き出す
- 1回目の高圧洗浄(ボディの汚れとタイヤに付いた洗剤を洗い流す)
- 再度シャンプー液を作ってミット洗車
- 2回目の高圧洗浄(ボディに付いた洗剤を洗い流す)
- 拭き上げブースに移動して、すばやく拭き上げる
コイン洗車場にはシャンプー洗車や泡洗車のコースもありますが、それを使うことはありません。
これらのコースは「高圧洗浄→洗車タイム→高圧洗浄」がセットになっていて、それぞれに制限時間があるので、落ち着いて丁寧に洗う時間が取れないのです。そのため、5分間の水洗いコースを2回やっています。この方が落ち着いて洗うことができます。
まずは天気を確認しよう
いちばん最初に考えるのは、洗車する際の天気や気温です。
なぜなら、できるだけ泡が乾きにくい天気を選んで行う必要があるからです。泡がすぐに乾いてしまうと、その部分にシミができたりなど、トラブルの原因となってしまいます。
そのため、たとえば「気温が高くない曇りの日」などがベスト。快晴の昼間とかにやったら一瞬で乾いていくので最悪のコンディションですよ。外で活動するのは晴れてた方が気持ちいいかもしれないけど、洗車は絶対にダメです。
だからといって夜にやると、照明のある洗車場であっても暗くて汚れがよく見えないので、おすすめしません。手洗い洗車はボディ状態の確認の意味もあり、明るいときにやった方がいいのです。
最初にタイヤ・ホイールを洗う
タイヤやホイールに付いた砂埃や鉄粉を舞い上げないように、まずはタイヤとホイールから洗います。
本来なら一度タイヤを濡らしてから洗うのがセオリーなのですが、ちょっとしか水を使わない状況で水洗いコースに課金するのは勿体なさすぎる。そのため、いきなりシャンプー液で洗うようにしています。できるだけたっぷりのシャンプー液を使って、水で濡らす程度の効果があるように心がけます。
洗うのは以下の3か所。
- タイヤ側面
- ホイール表面(ナット部分も含めて)
- ホイール内部
本当は、タイヤ側面は専用ブラシを、ホイール表面はホイールミットなどを、それぞれ使う必要があるのですが、今のところはそこまでこだわっていません。オートバックスで買った激安のスポンジを使っています。
また、ホイール表面は凹凸が多いし、ナットの部分などは奥まっていて、スポンジやミットでは洗いにくいこともあります。そういうときはディテーリングブラシを使って汚れを動かしています。これは毎回じゃなくて、丁寧に洗いたいときにやる程度。
そして、ホイール内部は専用のマイクロファイバーブラシを使っています。固めのブラシやコンパクトなマイクロファイバーブラシも試したけれど、あまりしっくりきませんでした。マイクロファイバーブラシだとシャンプー液をたくさん含ませることができるし、大きいものは奥の方まで到達させやすいです。
タイヤ・ホイール洗車で使っているアイテム
バケツ
シャンプー液を作るのにバケツは必須です。僕が使っているバケツが終売になったようで、ここには同メーカーの類似製品を掲載。洗車用じゃなくても普通の家庭用のバケツでも全然OK。
ホイールブラシ(マイクロファイバー)
いろいろなホイールブラシを使ってみて、これがいちばん使いやすかったです。乾いているときに毛が抜けやすいのが難点だけど、濡らしてしまえばしっかり使えます。
適当なスポンジ
下回りには適当なスポンジを使っています。この商品じゃないけど、オートバックスで同じような適当なやつを買いました。
カーシャンプー
カーシャンプーはこれが定番ですよ。こだわったらいろんな商品があると思うけど、こだわらないならこれで十分。
ディテーリングブラシ
ホイール表面やナットなど、細かい凹凸のある部分を洗うためには、このようなディテーリングブラシが必須です。

余裕があれば、泡を吹きかけて細かい部分をブラシで
そして、これは毎回やっているわけではないのですが、泡をかけて汚れを浮かせながら、ディテーリングブラシで細かい部分の汚れを掻き出すこともあります。
特に夏の高速道路を走った後は前面に虫が大量に付き、走行中にガビガビに乾いてしまうので、通常の洗車では取り切れません。そのため、1回目の高圧洗浄をやる前にある程度ふやかしておく必要があり、そのためにフォームガンでシャンプーの泡を吹きかけておきます。
それと合わせて、ヘッドライト、ドアノブ、ボディパネルの接合部、窓のゴムパッキンなど、細かい部分に蓄積した汚れをディテーリングブラシで掻き出しておきます。
白い車だと特に、こういう細かい部分に隠れていた汚れが雨水で流れ出し、黒い線になることがよくあります。でも、洗車時にディテーリングブラシで掻き出しておくだけで全然違うんですよ。黒い線ができることは少なくなるように思います。
ディテーリングで使っているアイテム
カーシャンプー
フォームガン
フォームガンの中に水とシャンプー液を入れて、泡を吹きかけます。蓄圧式のポンプになっているので、クリーミーな泡をボディ全体にかけることができます。
ディテーリングブラシ
1回目の高圧洗浄
その後、水洗いコースで高圧洗浄を行い、ボディー全体に付着した砂埃などを水で洗い流します。この工程をしっかりやらないと、次のミット洗車のときに砂を引きずってしまい、ボディに傷をつけてしまいます。だからとても重要な工程です。
基本的には上から下に流していくイメージです。そのため、最初はルーフから流し始めて、フロントガラスやボディ側面、ボンネット、ボディ正面、ボディ後面といった具合です。小さなこだわりは、給油口のカバーを開けておいて、その中の砂埃も一緒に洗い流すことかな。
タイヤに関しても先ほどの工程のシャンプー液が残っているので、よく流します。また、ホイールハウス内に付着した泥汚れも、この工程で一気に流します。
ここで使っているアイテムは特になし。洗車場の高圧洗浄機をそのまま使います。

たっぷりのシャンプー液でミット洗車
1回目の高圧洗浄で砂埃を流したら、次は本格的な洗車に入ります。
ここでは、たっぷりのシャンプー液を使って、ボディ全体を優しく洗っていきます。最初に洗った部分からどんどん乾いていくので、この工程はいかに効率よく、かつ丁寧に進めるかがポイントになります。そうしないとボディにシミができます。
僕はいつも、泡いっぱいのシャンプー液を作って、そこに洗車ミット(スポンジ)をたっぷり浸してから洗い始めます。泡たっぷりのミットで、ボディをなでるように優しく洗うイメージ。
ここで大事なのは、絶対に力を入れないこと。ゴシゴシこすると、小さな砂粒を引きずって傷の原因になってしまいます。あくまで泡のクッションで、汚れを浮かせる感覚です。
そして、こまめにミットを洗うのが重要。巷では「泡を作る用のバケツ」と「ミットを洗う用のバケツ」を2つ用意することも推奨されるくらいなので、シビアに考えた方がいいです。
ただ、僕は面倒なのでバケツは1個でやってます。泡を作る用のバケツにミットを浸してしっかり洗い、そのまま泡を掬ってボディへ。1〜2往復したらミットを裏返し、さらに1〜2往復したら洗う。この繰り返しです。
洗う順番は基本的に「上から下へ」だけど、あんまりこだわらなくていいんじゃないかと思っています。なぜなら頻繁にミットを洗うし、自分が分かりやすい順番で進めないと洗い忘れるからです。最近の僕の場合は以下のような順番で洗っています。
- 右側ルーフ → 右側面 → 右側フェンダー
- フロントガラス右側 → ボンネット右側
- グリルやヘッドライト
- 左側ルーフ → 左側面 → 左側フェンダー
- フロントガラス左側 → ボンネット左側
- リア
CX-60はボディが大きくて洗うのが大変。そしてルーフは手が届かないので、折りたたみ式の踏み台を使っています。洗車場によっては脚立があるところもあるだろうけど、慣れない脚立をボディにぶつける可能性を排除したいので、自分の踏み台を使います。
2回目の高圧洗浄
ミット洗車が終わったら、次は2回目の高圧洗浄で泡を洗い流していきます。もう一度、通常の水洗いコースでやります。
ここでも意識しているのは「上から下へ」。ルーフから始めて、フロントガラス、ボディ側面、ボンネット、リア、最後に足回り、という順番で進めます。上に汚れが残っている状態で下を流しても意味ないので、しつこいくらい上から順番に。
泡だけじゃなくて、ミット洗車で浮かせた汚れも一緒に流していくイメージです。タイヤやホイールに付いた泡も、この工程で一緒に流します。拭き上げのときまで泡を残さないよう、全部流しきりましょう。
こちらも洗車場の高圧洗浄機をそのまま使うので、紹介するアイテムは特になし。

すばやく拭き上げる
泡と汚れを流し終えたら、拭き上げブースに車を移動して、すぐに拭き上げに入ります。水滴をそのまま放置するとシミの原因になってしまうから、ここは時間との勝負です。
僕が使っているのは、吸水性が高いマイクロファイバークロス。軽く触れるだけで水を吸い取ってくれるので、ゴシゴシ擦る必要がなく、ボディへの負担も少ない。大判のものを2枚使ってボディ全体を拭き上げます。
基本は「大きく広げてボディの上を滑らせる」がルール。僕の場合はミット洗車と同じ流れで、上から順番に拭き取っていきます。
- 右側ルーフ → 右側面 → 右側フェンダー
- フロントガラス右側 → ボンネット右側
- グリルやヘッドライト
- 左側ルーフ → 左側面 → 左側フェンダー
- フロントガラス左側 → ボンネット左側
- リア
大判のマイクロファイバークロス2枚で全体をざっと拭き上げた後、小さなマイクロファイバークロスに持ち替えて、ヘッドライトやグリルなどの細かい部分を拭いていきます。また、ドアの内側や、サンルーフの隙間、ホイールなども、くまなく拭いていきます。
高圧洗車を行うとエンジンルームにまで水が入り込むので、ボンネットを開けてちゃんと拭き上げるのが小さなこだわりです。エンジンカバーにも砂埃がかなり溜まっているので、このときに一緒に拭き取っています。
拭き上げで使っているアイテム
マイクロファイバークロス(大判)
一気に拭き上げるためには大判のマイクロファイバークロスが必須ですね。僕はこの商品を使っていて、CX-60の場合は2枚でちょうどいいです。
マイクロファイバークロス
細かい部分はハンドタオルくらいの大きさのマイクロファイバークロスを使います。頻繁に持ち替えて、1回の洗車で5枚くらい使うイメージです。
踏み台
拭き上げ時にも踏み台が活躍しています。ルーフに手が届かない車だと必須です。
日常的なメンテナンスで、白さは守れる
白い車は初めて乗ったのですが、確かに汚れが目立ちやすい。これまでは濃色系ばかりを乗り継いできたので、砂埃ばかり気にしていました。でも、白い車は砂埃だけじゃなくて、日頃のメンテナンスの成果が目に見えて現れるように思っています。
たとえば、錆びた茶色い鉄粉とか、黒ずんできた水垢とか。濃色の車では気にならなかった小さな汚れも、白いボディではすぐに目に映ります。ボディが白いから、どんな色の汚れが乗っても分かるんですよ。だから定期的なコーティングと日頃のメンテナンスが重要。
今回紹介したメンテナンス方法は、どれも特別なテクニックじゃありません。コイン洗車場で手を動かしながら、試行錯誤してきた結果、自然とたどり着いたものばかり。
大事なのは、「完璧を目指すこと」ではなくて、できるときに、できるだけ、手をかけること。その積み重ねが白い車の美しさを守り、きっと愛着にもつながっていくはずです。