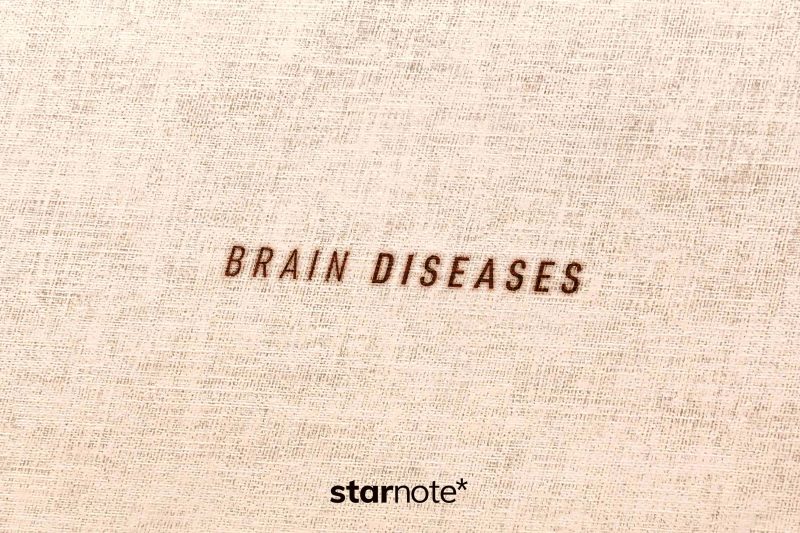実用化されれば救われる人はたくさんいると思います。
この記事には広告が含まれています。
アンメットニーズの多い「脳疾患」
数々の病気を治療できて健康寿命が大いに延びた現代ですが、未だに治療法が確立されていない疾患もたくさんあります。その最たるものが「脳疾患」です。
脳疾患の治療が困難な理由として、以下の2つの原因が挙げられます。
- そもそもターゲットが不明 —— アルツハイマーにおけるアミロイドβ仮説
- ターゲットは明確だけど送達できない —— 脳腫瘍
今日のトピックの重点は後者ですが、一応前者から触れておきましょう。
ターゲットが不明で治療薬の開発が進まない
僕はあまりアルツハイマー領域には詳しくないですが、最近はアミロイドβ仮説の正しさが議論になっていますね。
これまでは「アミロイドβの蓄積を抑えて老人斑の形成を防ぐことができれば、アルツハイマー病を予防(治療?)できる」という〈アミロイドβ仮説〉が定説でしたが、最近ではどうやらそうではなさそうだぞという議論もされています。
→ アルツハイマー病のアミロイドβ仮説は死んだのか?:日経バイオテクONLINE
こんな状況になってくると「アルツハイマー病の治療ターゲットはどこなの…?」という話に逆戻りです。
つまり、治療すべきターゲットが明らかにならないと医薬品の開発も進まないのです。人間の脳は完全に解明されていないので、このようなブラックボックスがたくさんあります。だからアンメットニーズも多い。
ターゲットは明確だけど送達できない
一方、治療すべきターゲットは明確なのに「脳内に送達できない」ことがボトルネックになっている疾患もあります。たとえば脳腫瘍、脳の中にがんができている病態です。
動物レベルでは脳内に送達さえできればドキソルビシンが効果を示す(Aryal M et al. J Control Release, 2013;169:103–11 PubMed)という報告もあるし、HER2(+)の乳がんはHER2(+)のままで脳に転移する(Saunus JM et al. Int J Mol Sci, 2017;18:E152 PubMed)ので、送達さえできればトラスツズマブ(ハーセプチン®)が効果を示す可能性もあります。
そこで課題になるのが、〈どうやって血液脳関門を越えて治療薬を脳内に送達するか〉という点です。
ヒト(に限らず脊椎動物)の脳には「血液脳関門(Blood Brain Barrier: BBB)」と呼ばれる強固なバリアがあります。これがあることで、毛細血管から脳の中に余計な物質が入り込まないようになっています。
BBBは生きていく上では超重要な機構なのですが、こと薬物送達に関しては厄介な存在です。BBBにおいては薬は異物として扱われるので、簡単に通過することができません。特に水溶性の薬物を通すのはほぼ不可能。
でも、それを何とか解決しようという研究が行われています。僕の研究はこちら側です。
BBBを越えて脳内へ薬物を送達する方法
まだ動物実験レベルのものが多いですが、BBBを越えて脳内へ薬物を送達する方法として、以下のような方法が提唱されています。
- 脳内または髄腔内に直接投与する
- トランスポーターを使う
- トランスサイトーシスさせる
- 膜透過ペプチドを使う
- 鼻から吸収させる(Nose-to-Brain: N2B)
- バブル製剤+超音波でBBBをこじ開ける
1. 脳内または髄腔内に直接投与する
脳と脊髄はつながっていて、その中には脳脊髄液(Cerebrospinal fluid: CSF)という液体が流れています。そのCSFの中に直接投与すれば、脳や脊髄に薬を送り込むことができます。
ただし、かなり侵襲的で患者負担も大きく、感染リスクも上がるので、あまり頻繁に行われるものではありません。リスクよりベネフィットの方が上回ると判断された場合にのみ行われます。
たとえば、MRSAを原因菌とした髄膜炎におけるバンコマイシンの脳室内投与とか。そのあとの薬物動態をマウスで観察したのが、僕が片手間で書いた論文です。
2. トランスポーターを使う
脳内の毛細血管上に発現しているトランスポーターを使う方法で、有名なのはL-DOPA(レボトパ)の送達です。
アミノ酸であるL-DOPAは、毛細血管上のアミノ酸トランスポーターに認識されて脳内に入り込むことができます。そのあと脳内でドパミンに代謝されて薬効を発現するという仕組みです。
今はこのような古典的なものだけではなくて、グルコーストランスポーター(GLUT)を認識するナノマシンの開発とかも進んでいるようです。
→ 共同発表:グルコース濃度に応答して血中から脳内に薬剤を届けるナノマシンを開発
3. トランスサイトーシスさせる
脳内の毛細血管の血管壁を通過させる方法です。どちらかというと分子生物学寄りの話になってしまうので、僕の知識では解説できない(すべきではない)です、ごめんなさい。一応こんなアプローチもあるということで。
4. 膜透過ペプチドを使う
ペプチドとはいくつかのアミノ酸がペプチド結合でつながったものですが、特定のアミノ酸配列からなるペプチドがBBBを通過できるという知見が得られています。
そのペプチドに薬物を結合させて血管内投与すると、BBBを透過できるペプチドと共に薬物を脳内に送達できるらしいです。このようなペプチド配列のことを「シャトルペプチド」と呼んだりします(Oller-Salvia B et al. Chem. Soc. Rev. 2016;45:4690–4707 PubMed)。
5. 鼻から吸収させる(Nose-to-Brain: N2B)
鼻の中のにおいを感じ取る部位は脳と直接つながっていて、その部分にはBBBが形成されていません。これを利用して鼻から脳内に送り込むのが「Nose-to-Brain」という方法です。
具体的にどのようなアプローチがされているのかは僕もあまり詳しくないですが、ここで挙げた6つの中では研究している人が比較的多いような(勝手な)イメージ。
報告によるとペプチドサイズの比較的大きな薬物まで送ることができる(Samaridou, E. & Alonso, M. J. Bioorganic Med. Chem. 2018;26:2888–2905 PubMed)ようで、実用化されれば患者にとってはいちばんお手軽な方法かなーと思います。
6. バブル製剤+超音波でBBBをこじ開ける
僕が行っていたのはこの方法です。
リポソームの中に超音波造影ガスを封入した「バブル製剤」というのがあるんです。日本で買える既承認薬だと第一三共から出てるソナゾイド®という超音波診断用の造影剤。実際に研究で使っていたのは違うものですが、まぁ似たような感じです。
これを血管内投与のうえで脳に超音波を当てると、バブル製剤が「キャビテーション」という動きをします。要するに破裂したりするんですが、そのエネルギーを使ってBBBをこじ開けることができます。
具体的には、脳内毛細血管の内皮細胞どうしの密着結合を開裂させて、空いた隙間から血管内投与した薬を送り込みます。言葉で説明するよりこの動画を見た方がわかりやすいかな。
この方法のアドバンテージとしては、
- 超音波照射を調節することで、送達部位をピンポイントで絞ることができる
- 低分子薬はもちろん、ペプチド、抗体など大きな分子まで脳内に送り込むことができる
- フランスやカナダで臨床試験がされるほど研究が進んでいる(Carpentier A et al. Sci Transl Med, 2016;8:343re2 PubMed)
といったところでしょうか。逆にディスアドバンテージとしては、
- たとえ一過性でもBBBを壊すことになるので、その後の回復が課題
というものがあります。このあたりはリスク-ベネフィットのバランスを探りながら適応することになるんじゃないかなーと思っています。
まとめ
脳疾患の治療が困難な理由として、
- そもそもターゲットが不明
- ターゲットは明確だけど送達できない
このような原因がありました。
後者の送達に関して、現在行われている薬物療法は、限定的にトランスポーターを使う(L-DOPA)か、思いっきり薬物の脂溶性を上げて毛細血管を無理矢理透過させるか、という古典的なものばかりです。
ここに大きなブレークスルーがあると、脳疾患の治療満足度は劇的に改善する可能性があります。だから送達法の開発が今後の脳疾患において重要なファクターであることは間違いありません。
とか言いつつ僕はもう研究していないのですが、引き続き動向を見守っていきたいと思っています。今回は以上です。